監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等
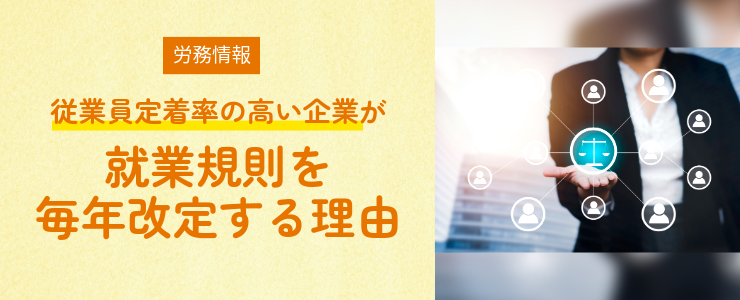
今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ よくある質問とそれに対する回答
◆ 管理職も知らない?「絵に描いた餅」になった就業規則
◆ なぜ就業規則は「時代遅れ」になってしまうのか?
◆ 「トラブルが起きてから」では遅い理由
◆ 採用力と定着率を高める「就業規則」の戦略
【 KING OF TIME 情報 】
◆ KING OF TIME 勤怠管理
よくある質問とそれに対する回答
Q. 就業規則の改定は大変ですし、従業員が見る機会もあまりないので、毎年変える必要はないのではありませんか?
A. 労使間トラブルの抑止や従業員満足度の向上、採用力の強化を行っていくためにも、就業規則は、法改正の都度、また判例動向や時代の流れなどを加味して、毎年、場合によってはそれ以上の頻度で改定していくことが必要です。
管理職も知らない?「絵に描いた餅」になった就業規則
就業規則は、当該企業における労働条件や服務規律を定めたもので、「企業の憲法」とも称されることがあります。しかし、その重要性にもかかわらず、管理部門以外には内容が浸透しておらず、管理職層ですら正確に理解していないケースも少なくありません。
現場の管理職がルールを把握していない場合、その影響は深刻です。例えば、部下からの育児休業や子の看護等休暇の申し出に対し、知識不足から不適切な対応を取り、ハラスメント(マタハラ、パタハラ等)に該当してしまうリスクがあります。あるいは、無自覚に違法な長時間労働を指示するなど、労務管理に一貫性が担保されません。結果として従業員間に不公平感を生じさせ、職場全体の士気の低下を招く原因となります。管理職に対する就業規則の教育・研修も伴わなければ、規程は実効性を持ち得ません。
また、労働時間制の適用には就業規則への記載が要件となっているにもかかわらず、規程を整備することなく、制度を導入してしまっているケースもあります。例えば、有名ハンバーガーチェーンが1ヵ月単位の変形労働時間制を採用していたものの、就業規則に必要な記載を行っていなかったために、その適用を無効とされた裁判例も存在します。適切な勤怠管理を行う前提として、就業規則の見直しは必要不可欠なわけです。
「ネット上に公開されている雛形(テンプレート)を流用したままで自社の実態に即していない」「法改正に長期間対応できていない」といった課題も多く聞かれます。例えば、IT企業において製造業向けのような服務規律が残存しているなど、実態と乖離した規程は無用な混乱を招くのみです。
「内容が良ければ問題ない」というわけでもありません。法律上、就業規則は社内に周知する義務があり、「周知」は就業規則が効力を持つための要件の一つとされています。社内ポータルサイトへの掲載や書面での配布など、従業員がいつでも閲覧できる状態にしておく必要があります。「周知」が不十分と判断された場合、就業規則の効力が否定され、企業側が意図した規律(懲戒処分の根拠など)を適用できなくなるリスクさえ存在します。
実態と乖離した、あるいは周知されていない規程は「絵に描いた餅」であり、コンプライアンス意識の低下を招くことも懸念されます。
なぜ就業規則は「時代遅れ」になってしまうのか?
労働・社会保険関係法令は、近年、毎年のように改正が行われています。「法改正」への対応は、法令違反(コンプライアンス違反)を回避するために不可欠です。近年では、育児・介護休業法、労働施策総合推進法(ハラスメント関連)など、企業の労務管理に直結する改正が頻繁に行われています。
また、「判例」の動向も重要です。法律に変更がなくとも、裁判所の「解釈」によって、いまの就業規則の記載では不十分になる可能性がありますので、判例で示された基準を就業規則に反映させることは、将来の紛争予防において極めて有効です。
さらに、リモートワーク、副業・兼業、ダイバーシティ、あるいは従業員のメンタルヘルス対策といった「時代の流れ」への対応も不可欠です。
これらに対応しないまま放置することは、法的なリスクのみならず、従業員の信頼を損ね、優秀な人材の流出を招く事態にも直結します。
「トラブルが起きてから」では遅い理由
長期間改定していない就業規則は、単に「古い」という問題があるだけではありません。法改正の内容に反する記載が残っており、その記載が無効となっている可能性があります。法律と就業規則の記載が抵触する場合、当然ながら法律の規定が優先されるからです。
そのような就業規則を放置することは、労使間トラブルの抑止力として機能しないばかりか、企業のガバナンス体制への不信感を招きます。「法令遵守の意識が低い」という疑念は、従業員や取引先、さらには消費者からの信頼を失墜させかねません。
特に現代社会においては、こうした内部体制の不備がSNS等を通じて瞬時に拡散されるリスクもあります。一度「ブラック企業」との評価が拡散されれば、結果として違法性がなかったとしても、企業の社会的評価に深刻かつ長期的なダメージを与えるリスクが極めて大きいと言えます。
「これまで労務トラブルが発生していなかった」という事実は、必ずしも就業規則が適切に機能していたことを意味しません。それは潜在的な問題が表面化していなかった、あるいは、従業員が問題を認識しつつも(企業文化や手続きの不備により)声を上げていなかっただけ、というケースも多いと考えられます。
トラブルが顕在化した際、会社を保護する役割を果たすべき就業規則の整備が不十分であったために、企業側が一方的に不利な結果を招くリスクも少なくありません。例えば、服務規律にSNSの私的利用や情報セキュリティに関する明確な規定がなければ、従業員による不適切行為(機密情報の漏洩や企業の誹謗中傷)に対する懲戒処分が「処分の根拠規定が存在しない」として無効と判断されるリスクがあります。有事の際に機能する規程整備が不可欠です。
採用力と定着率を高める「就業規則」の戦略
労働力人口が縮小する昨今、労働力の確保は最重要課題です。「コンプライアンスを重視し、働きやすい環境を構築する」という姿勢は、従業員満足度の向上だけでなく、採用活動においても決定的な要因となり得ます。
現代の求職者は、給与水準のみならず、ハラスメント対策の具体的内容、育児・介護支援制度の充実度、リモートワークやフレックスタイムといった柔軟な働き方の可否などを、口コミサイトやSNSを通じて厳しく評価します。
就業規則が時勢に適合していない、あるいは内容が不透明であるという事実は、採用競争力の低下に直結すると言えます。また、既存従業員が他社の整備された労働条件と比較し、自社へのエンゲージメントを低下させ、離職を招く(=定着率の低下)可能性さえあります。
とはいえ、難解な法律用語が多い就業規則は、単に社内ポータルサイトに掲載するだけでは熟読されません。法的な正しさを担保しつつも、平易な言葉を用いた解説資料の配布、具体的なケーススタディを交えた研修の実施など、従業員が「自分たちのルールである」と理解できるような周知の工夫が重要です。
ひとつのアイディアとして、変更後の就業規則を反映した雇用契約書を毎年取り交わすという方法もあります。このとき電子契約サービスを活用すれば、省力化を図りながら、従業員が受け取った(≒内容を把握した)という記録を残すこともできます。
就業規則の定期的な見直しと従業員への適切な周知は、単なる法令遵守(コンプライアンス)の範疇を超え、企業のレピュテーションリスクを管理し、従業員との信頼関係を構築し、ひいては持続的な成長を支える経営戦略の重要な基盤であると言えるでしょう。
KING OF TIME 情報
最近、自由な働き方を取り入れるため、フレックスタイム制などの変形労働制導入に向けたお問い合わせも増えています。
今回の記事では、就業規則の不備が招くリスク、特に労働時間制度の運用における規程整備の重要性を解説しました。就業規則の記載不備などによって、せっかく導入した変形労働時間制が無効になるリスクを回避するためにも、以下の記事で変形労働時間制のルールを今一度ご確認ください。
各記事では、KING OF TIME 勤怠管理の設定ポイントもあわせて解説しています。
間違えて運用していませんか?【 1か月単位の変形労働時間制(その1)】 ~日、週、月単位の残業設定を見直そう~ >>>
間違えて運用していませんか?【 1か月単位の変形労働時間制(その2)】 ~日、週、月単位の残業設定を見直そう~ >>>
▼1年単位の変形労働時間制間違えて運用していませんか?【1年単位の変形労働時間制(その1)】 ~導入する際の注意点と残業計算のルール~ >>>
間違えて運用していませんか?【1年単位の変形労働時間制(その2)】 ~年の途中で入退社が発生した場合やシフト変更の注意点など~ >>>
▼フレックスタイム制フレックスタイム制を検討する際のポイント ~外してはいけないフレックスのルール~ >>>
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








