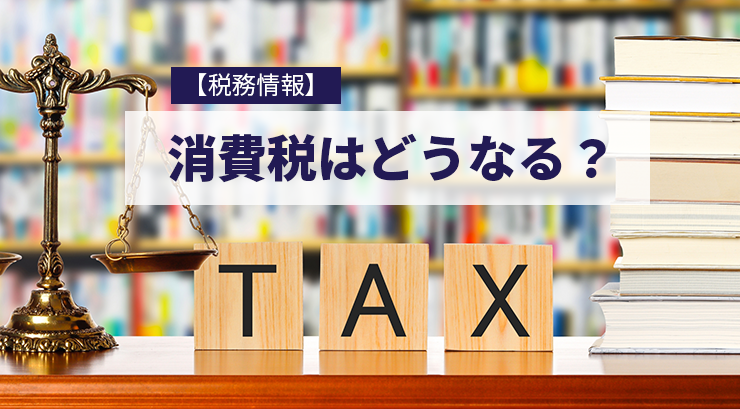
今週のピックアップ
◆ 輸出免税の見直し
◆ 最近の消費税に関する議論
◆ インボイス制度と消費税減税の関係
◆ まとめ
輸出免税の見直し
総合経営サービスの植松です。
今回は、消費税についてです。
2025年の税制改正では、消費税に関する大きな改正はありませんでしたが、訪日外国人向けの免税制度(輸出免税)に関する見直しが行われました。
これは、外国人旅行者が免税店で商品を購入する際の消費税の取り扱いを変更するものです。従来は、その場で消費税が免除されていましたが、改正により、店舗での購入時は通常どおり消費税がかかり(徴収され)、外国人旅行者が帰国する際、空港などで所定の手続きを経ることで消費税分を還付(免除)する仕組みとなります。なお、この改正が完全に実施されるのは、2026年11月1日以降の商品購入からです。
改正の目的の一つは、免税制度を悪用した不正(例えば、購入した商品を日本国内で消費したり、転売して利益を得るなど)の防止です。
転売などはそれ自体を直接防ぐことはできませんが、消費税抜きで購入することができなくなるため、一定の抑止効果が期待できます。また、空港などでの出国時の手続きを行うのであれば、現物確認などもありますので、不正な消費税の免税利用はしにくくなるでしょう。
さらに、空港などでの手続きには購入品の現物提示や書類の整備など、一定の時間と手間がかかります。事業者の方で消費税の還付申告をされたことがある方であればお分かりになるかと思いますが、還付申告時には、還付となる理由について、明細書や請求書、支払いが確認できる資料など、多くの提出物を求められます。同様に考えると、「簡単には還付されない仕組み」であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。こうした点からも不正の抑止になるといえるでしょう。
最近の消費税に関する議論
所得税の基礎控除などの議論が一段落し、今度は「消費税をどうすべきか?」という議論が活発になってきています。議論の中では、「1年間限定で食料品0%課税」や「税率を一律5%に減税」、はたまた「廃止」など、さまざまな意見が出てきており、今後の大きな争点となりそうです。
消費税の計算に関しては、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、「0%課税」と「非課税」は全く異なります。
少々専門的な話になりますが、消費税の計算上、売上を「課税取引」「非課税取引」「対象外取引」の三つに区分する必要があります。消費税(仕入税額控除)を計算する上で、売上に対する課税取引となる売上の割合(課税売上割合)が重要なポイントとなります。
例えば、課税取引の売上が700円、非課税取引の売上が300円、対象外取引の売上が100円の場合、対象外取引は計算に含めないため、課税売上割合は70%(700円 ÷ [700円 + 300円] )となります。
消費税は、原則として受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引いた差額を納付するか、または還付を受ける制度です。
食料品の消費税が「0%課税」であれば、食料品のみを販売している事業者の課税売上割合は100%ですが、「非課税」であれば課税売上割合は0%となります。
「0%課税」の場合、課税売上割合が100%であるため、仕入れやその他の経費に含まれる消費税額の還付を受けることができます。一方、「非課税」の場合は課税売上割合が0%であるため、いくら経費などで消費税を支払っていても、基本的にその消費税額の還付は受けられません。
この問題は「非課税」という制度に起因するため、輸出売上と同様に「0%課税」にすれば解決するはずですが、消費税法の導入以降、この点は重要な論点として議論されていません。輸出時に消費税を還付する輸出免税制度については、実質的に輸出補助金ではないかとの賛否両論がありますが、こうした国内制度における不統一も、その議論の一因となっているように思われます。
インボイス制度との関係
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、今なお、実務においてはさまざまな課題が見受けられます。
例えば、大手企業であっても請求書に登録番号の記載がないケースが散見されます。これは必ずしも誤りというわけではなく、納品書に登録番号の記載があり、かつ請求書がその他の要件を満たしている場合には、両方を保存することで適格請求書として認められることがあります。
しかし、会計事務所の立場からすると、請求書に記載がなく納品書に記載があると言われても、正直なところ、そこまで確認しきれないため、請求書にすべての情報を記載してほしいというのが本音です。
先述のとおり、現在、「消費税をどうすべきか?」については、さまざまな意見が出てきています。これらの意見がそれぞれ実現した場合、インボイス制度との整合性はどのようになるのでしょうか。
まず、「食料品0%課税」となった場合、現行の軽減税率8%が0%に引き下げられることになります。そのため、インボイス制度(適格請求書)では、軽減税率の表記を8%から0%へ変更するだけで、制度的には現行の仕組みをある程度維持したまま対応が可能と考えられます。
「食料品非課税」となった場合は、「0%課税」とは根本的に異なります。非課税となると、その売上に対応する仕入税額控除ができなくなり、事業者にとっては税負担が増加するなど、大きな変化が生じます。制度全体の見直しが必要となり、実務上の負担も重くなる可能性があるため、これはあまり現実的とは言えないでしょう。
次に「一律5%課税」となる場合には、そもそも複数税率を前提とした適格請求書そのものの必要性が薄れます。すべての取引に単一の税率が適用されるため、税率ごとの明示や区分記載の要件も不要になるからです。ただし、インボイス登録制度自体には、登録番号を用いた取引先の管理といった目的もあるため、制度そのものが完全に廃止されるとは限りません。
最後に、現実的には考えにくいですが、「消費税が廃止」されれば、当然インボイス制度そのものが不要になります。課税そのものが行われない以上、仕入税額控除の制度も不要になり、適格請求書の発行・保存義務もなくなるでしょう。
いずれのケースにおいても、消費税の見直しとインボイス制度の見直しは表裏一体であり、一方だけを変更することは現実的ではありません。制度の公平性、簡素性、実務負担のバランスを考慮しつつ、現場の声を反映した柔軟な見直しが求められていると考えます。
消費税を食料品のみ0%にする場合、飲食店における売上(サービス提供)の10%課税に変更がないとすると、飲食店の消費税納税や資金繰りは非常に困難になるため、一律5%へ減税する方が効率的かつ効果的ではないでしょうか。
個人的には、インボイス制度自体が完全に悪いとは思いません。しかし、この制度を運用するには業務が煩雑になり、ミスした場合の取引先への影響などを考慮すると、実務的な負担は大きく、特に零細企業がすべてを適正に行うことは難しいのが実情です。
複数税率については、生活必需品の負担軽減を目的とするとされていますが、結果として制度が複雑化したり、将来的な消費税率引き上げの口実にされたりするのではないかという懸念があります。そのため、シンプルな制度が最良であると考えると、やはり単一税率が望ましいです。
まとめ
2022年、2023年と連続して平均所得が下がっている中、納税と社会保険の負担はむしろ増加傾向にあります。これでは、家計も事業も厳しくなる一方です。こうした状況への対応はスピーディに行ってもらいたいと思います。
また、生活支援や景気回復の観点からは、消費税廃止がベストですが、税率を下げるにしても、「とりあえず」の暫定措置ばかりでは、本質的な改革が先延ばしになるだけです。本質的な改革が難しくとも、その時々の情勢に合わせて見直しが行われていくことを期待します。
監修者紹介
税理士法人総合経営サービス 植松 伸
下町生まれの税理士の植松伸です。
税理士になる前は建設系の労働組合で働いていたので、建設業等の許認可や健康保険事務組合の知識もあり、それらの業務を弊社グループ内へつなぐことも大事にしています。
趣味は観賞魚飼育で、現在自宅に水槽が10個あります。
魚を眺めたり、水の音はとてもリラックスできるのですが、水槽の掃除等のメンテナンスに時間がかかるので、ちょっと増やしすぎたと反省する毎日です。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








