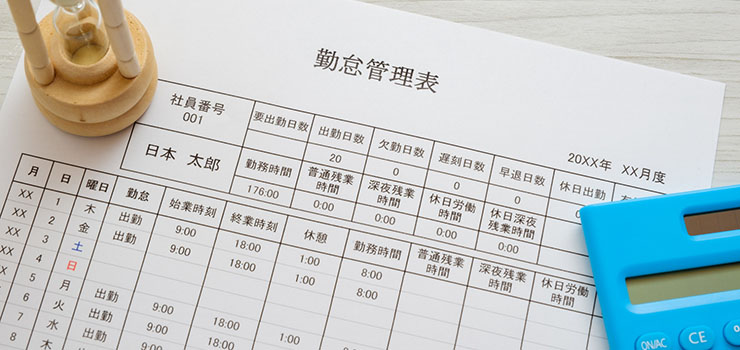
近年、働き方の多様化や法令の厳格化、人手不足などの影響から、中小企業における勤怠管理の重要性が高まっています。手作業やExcelでの勤怠管理のままでは業務に負担がかかり、入力ミスや法令違反につながる可能性も否定できません。
こうした状況を改善するには、勤怠管理システムの導入が有効です。特定業務の効率化だけでなく、企業全体の生産性向上やコンプライアンスの強化も期待できるでしょう。
本記事では、中小企業に勤怠管理システムを導入する理由やメリット、選ぶ際のポイントなどを詳しく解説します。
❖ 勤怠管理システム導入で中小企業の業務を効率化!
❖ 中小企業に勤怠管理システムを導入する7つのメリット
❖ 中小企業向け勤怠管理システムを選ぶ際の9つのポイント
❖ 業種ごとの勤怠管理システム選びのポイント
❖ 中小企業向けの勤怠管理には「KING OF TIME」がおすすめ!
❖ まとめ
勤怠管理システム導入で中小企業の業務を効率化!
中小企業にとって、勤怠管理の効率化は業務全体の改善につながる大切な一歩です。ここでは、なぜ勤怠管理を見直すべきなのか、中小企業に合った勤怠管理システムの特徴と併せて紹介します。
◇ 中小企業に適した勤怠管理システムとは
中小企業では、限られた人員やリソースでもスムーズに導入・運用できる勤怠管理システムが求められます。打刻方法や機能が豊富で、従業員にも使いやすいようなシステムが適しているでしょう。
例えば、打刻方法は直行直帰やリモートワークなどの場面にも対応できるよう、複数の方法から選べると安心できます。機能面では、操作のしやすさはもちろん法改正への対応、給与システムとの連携、サポート体制の有無など、基本機能がしっかり備わっているかがポイントです。
また、長期運用するためには費用面も重要といえます。クラウド型であれば、初期費用無料や月額数百円のプランも豊富にあり、気軽に導入しやすいことが魅力です。
◇ 勤怠管理から着手するのがおすすめの理由
勤怠管理は全従業員が日々かかわる業務であり、労務管理の基盤となる重要な部分です。そのため、勤怠管理システムを整備することで全社的な業務改善につながることが期待できます。
紙やExcelでの手動管理は入力ミスや集計ミスが起こりやすく、担当者の負担も大きくなりがちです。こうした課題は、勤怠管理のシステム化を実施することで解決できます。
また、厚生労働省のガイドラインでは、ICカード打刻やログイン履歴などによる「客観的な記録」が推奨されており、自己申告によるExcelや紙の記録は対象外とされています。怠ればガイドライン違反となるため、法令対応の観点からもシステム導入は有効です。
さらに、勤怠管理システムは比較的導入・運用の負担が軽く、労働時間の可視化や迅速な法令対応などの効果を実感しやすいのも特徴です。他業務におけるデジタル化を進めるきっかけにもなるでしょう。
参考: 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
中小企業に勤怠管理システムを導入する7つのメリット

ここでは、中小企業が勤怠管理システムの導入によって得られる、勤怠管理の課題解決イメージを紹介します。
◇ 1.手作業集計による工数とミスを解消して業務を効率化
勤怠管理システムを導入すれば、打刻から集計まで自動で処理されるため、ミスの軽減につながります。さらに、毎月の締め作業にかかる業務負担が減り、担当者や部署の作業効率向上も期待できるでしょう。ガイドライン遵守についても管理負担が軽減されます。
ほかにも、勤怠管理システムのデータ出力機能を使って給与計算ソフトと連携することで、手作業での転記が不要になり、給与処理の正確性と作業スピードが大幅に向上します。
◇ 2.多様な勤務形態の管理負担を軽減
シフト勤務やフレックスタイム制度、直行直帰、リモートワークなど、従業員ごとに勤務形態が異なる場合、すべてをExcelなどで管理するのは手間がかかります。
勤怠管理システムを導入すれば、勤務ルールを柔軟に設定でき、さまざまな勤務パターンに対応可能です。導入によって勤務状況がリアルタイムで可視化され、シフト作成や配置換えなど、管理も楽になります。さらに、全従業員の勤務情報を一元管理できるため、業務管理の透明性や公平性も向上します。
◇ 3.法改正への対応が自動化されて法令違反リスクを軽減
労働基準法や働き方改革関連法の改正があれば、労務担当者は制度更新や計算式の修正を行う必要があり、イレギュラーな業務が発生します。
しかし、勤怠管理システムは法令改正に合わせて自動アップデートされるため、この業務負担を大幅に軽減できます。常に最新の制度に準拠しており、法令違反となるリスクを軽減できるメリットもあります。
ほかにも、時間外労働や割増賃金の自動計算機能、長時間労働を検知するアラート機能などもあり、法令に則った労務管理をしっかりサポートしてくれます。
◇ 4.業務が特定の担当者に集中する「属人化」の課題を解消
勤怠管理の属人化も大きな課題です。業務が特定の担当者に依存していると、異動や退職時の引き継ぎが大きな負担となり、業務遅延や新たな担当者の離職につながりかねません。
その点、クラウド型の勤怠管理システムはデータを一元的に管理・共有できるため、業務フローの標準化が可能です。権限があれば誰でも同じ情報にアクセスでき、担当者が変わっても問題なく業務を継続できるでしょう。これにより、担当者の負担が軽減され、業務のブラックボックス化も防げます。
◇ 5.不正打刻や人為的ミスのリスクを防止
紙やExcelでの勤怠管理は、代理打刻や記録の改ざんなどの不正がしやすいことも課題です。勤怠管理システムでは、指紋や顔による生体認証やGPSによる位置情報を活用した打刻により、本人確認が強化されています。
さらに、打刻記録が自動的に保存され、編集履歴も追跡可能です。透明性の高い管理環境が確保されることで、不正やミスの防止につながるでしょう。信頼性の高い勤怠データが蓄積されれば、労働基準監督署や社内の労務監査への有効な対策にもなります。
◇ 6.就業状況の把握と人事戦略への活用が可能に
紙やExcelによる勤怠管理では、部門ごとの残業状況や労働時間の傾向などを分析するのに多くの時間と手間がかかります。
一方、勤怠管理システムならデータ分析やグラフ表示機能があるため、就業状況の可視化や傾向分析が簡単です。データを活用し、長時間労働の原因把握や部門ごとの人員配置の検討などが容易に行えます。数値に基づいた施策立案が可能になることで、組織全体の戦略的な人事管理にも役立てられるでしょう。
◇ 7.スマートで柔軟な働き方を実現し、従業員満足度を向上
出社して直接タイムカードなどを打刻する方法は、直行直帰やリモートワークに対応しづらい点が課題です。勤怠管理システムはスマートフォンやパソコンからの打刻に対応しているため、場所に縛られずに働ける環境が整います。
さらに、有給休暇や残業の申請・承認もシステム上で完結するため、従業員の利便性や業務効率も向上するでしょう。また、個人単位で勤怠情報を確認できるようになることで、自律的な働き方の促進と定着にも寄与します。
中小企業向け勤怠管理システムを選ぶ際の9つのポイント

中小企業がはじめて勤怠管理システムを導入する際は、自社の業務形態や運用に合ったシステム選びが重要です。ここでは、押さえておきたい9つの選定ポイントを紹介します。
◇ 1.打刻方法
勤怠管理の打刻方法は、自社の働き方や企業文化に合うものを選ぶ必要があります。おもな打刻方法は、次のとおりです。
・ICカード読み取り:Suicaなどをかざして打刻。専用端末やパソコン接続型がある。
・Web打刻:パソコンやスマートフォンのブラウザで打刻。直行直帰やリモートワークにも対応。
・スマートフォンアプリ:専用アプリで打刻。GPS連動やエリア制限が可能なアプリもある。
・生体認証:指紋や顔などで本人確認。不正打刻の防止に有効。
直行直帰やリモートワークが多い場合は、スマートフォンアプリやWeb打刻が役立ちます。まだ打刻方法を決めていない場合は、選択肢が豊富なシステムを選ぶことで柔軟な対応が可能です。
◇ 2.自社の業務形態へのマッチ度
自社の雇用形態や就業形態にマッチしているかどうかも重要なポイントです。正社員や契約社員、アルバイトなどのさまざまな雇用形態に対応しているか、勤務場所や時間が変則的な業務スタイルに対応しているかを確認する必要があります。
さらに、自社の勤怠ルールを柔軟に反映できるかどうかも重要な選定ポイントです。
◇ 3.シフト作成および管理のしやすさ
複雑なシフトパターンや人員配置に対応できる勤怠管理システムであれば、管理者の負担軽減につながります。
スタッフの希望を反映できる自動シフト作成機能や、人員の過不足をチェックする機能があると便利です。さらに、休暇や残業の申請・承認がシステム上で一元管理できれば、手間が減り管理もスムーズになるでしょう。
◇ 4.誰でも使いやすい操作性
勤怠管理システムを導入しても、定着しなければ意味がありません。担当者だけでなく、パソコンや機械に不慣れな社員でも直感的に操作できるシステムであることが理想です。
使いにくいシステムはミスを誘発し、逆に作業の負担が増えかねません。可能であれば、導入前に無料体験などで使用感を確認し、現場に合ったものを選びましょう。
◇ 5.法改正に適応したアップデートや便利な機能
勤怠管理に関連した労働基準法などの法案は定期的に改正されるため、法改正に自動で対応できるシステムを選ぶと安心です。自動アップデート機能がないと法改正に素早く対応できず、法律違反につながるリスクが高まります。
ほかにも、長時間労働の自動検知や有給取得義務者へのアラート機能などが搭載されたシステムもおすすめです。
◇ 6.ほかの業務ソフトとの連携
給与計算ソフトや人事管理システムなど、ほかの業務ソフトと連携ができるかも重要なポイントです。CSV形式でのデータ出力やAPI連携など、連携方法も含めて確認しましょう。他業務との連携は、勤怠管理だけでなく、社内全体の業務効率改善につながります。
◇ 7.業務形態に合わせたカスタマイズの有無
独自の休暇制度や奨励制度を導入している、という企業もあるのではないでしょうか。そうした独自の制度に対応できる、カスタマイズ性があるのかも重要です。
自社の運用ルールに合わせて柔軟に設定変更ができないと、システム外で作業しなければならなくなり、システムの導入効果が薄れてしまいます。自社に合わせてカスタマイズできる勤怠管理システムを探し、必要であれば、システム提供者へ対応の可否を問い合わせてみましょう。
◇ 8.初期費用やランニングコスト
導入にかかる初期費用や月額料金が明確であるか、自社の予算に合うか、追加オプションの有無、といったコスト面も確認しましょう。
中小企業の場合は、コストを抑えられるクラウド型のシステムがおすすめです。ただし、コストを抑えるために必要な機能をカットしすぎると、システム導入による効果が十分に発揮されません。現在の業務にかかっている工数や人件費と比較しながら、費用対効果の高いシステムを見極めることが大切です。
◇ 9.セキュリティ対策と充実したサポート体制
勤怠データは個人情報を含むため、暗号化やアクセス制限、改ざん防止などのセキュリティ機能が必須です。
また、併せてシステム提供者のサポート内容や運用体制についても確認しておきましょう。導入時や運用中に問題が起きた際には、電話やチャットによるサポートで迅速に対応してくれることが望ましいでしょう。トラブルが起きた場合の支援内容や追加費用の有無も、事前に把握しておくと安心です。
業種ごとの勤怠管理システム選びのポイント

勤怠管理システムは、業種ごとに必要な機能などが異なります。ここでは、5つの業種に分けて選び方のポイントを紹介します。
<業種別:勤怠管理システム選びのポイント>
| 業種 | 選ぶポイント |
|---|---|
| 製造業 | ・複雑なシフトに対応しているか ・生体認証や共通端末を使った打刻があるか(スマートフォンやタブレットなどを持ち込めない現場の場合) ・耐環境性のある端末か(端末を持ち込める現場でも安心して使える) |
| 建設業 | ・直行直帰や複数現場への移動に対応するGPS打刻や工数管理機能があるか |
| 飲食業 | ・短時間勤務や複数店舗の兼務に対応するシフト管理機能や打刻漏れアラート機能があるか |
| 介護・医療業 | ・複数の職種や雇用形態、夜勤などの複雑なシフト作成に対応しているか |
| 運送業 | ・多様な勤務形態に対応しているか ・拘束時間やインターバル管理、アルコールチェックなどと連携できるか |
上記はあくまで業種ごとの一例です。必要な機能は企業ごとに異なるため、自社に必要な機能を洗い出したうえで、システムの選定を行いましょう。
中小企業向けの勤怠管理には「KING OF TIME」がおすすめ!
ここでは、中小企業の勤怠管理におすすめの「KING OF TIME」を紹介します。
KING OF TIMEは初期費用がかからず、1人当たり月額300円(税抜)の低コストで全機能を利用できるクラウド型勤怠管理システムです。操作がしやすく、以下のような特徴があります。
・打刻方法は、ICカードやスマートフォン、パソコンログ、GPS、生体認証(指紋・顔)などに対応
・勤怠データ管理だけでなく、残業や休暇の管理、シフト作成、給与計算ソフトとの連携、労務アラートなど役立つ機能が充実
・独自の就業規則や変則勤務にも柔軟に対応
・法改正に対応した迅速なアップデート
・データ暗号化やアクセス制限など、安心のセキュリティ
30日間の無料体験ですべての機能をお試しいただけます。導入後のサポートも手厚く、初期設定支援やオンラインマニュアル、電話やチャットによるサポートもあるため、システムに不慣れな企業担当の方にも安心してご利用いただけます。
■ 無料体験のお申し込みはこちら >>>
■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>
まとめ
勤怠管理システムを導入することで、業務効率化や法令遵守、従業員満足度の向上などが期待できます。中小企業が勤怠管理システムの導入を成功させるには、自社の業務形態や規模に合ったシステム選びが重要です。打刻方法やコスト、操作性、サポート体制などの複数の視点で比較し、導入後の利用イメージを具体的に持つことが欠かせません。
「KING OF TIME」なら、多機能かつ低コストでサポート体制も充実しています。勤怠管理システムの導入を検討している企業の方は、ぜひ無料体験で使用感をお試しください。








