
本記事では、タイムカードの仕組みやメリット・デメリット、種類、適切な取扱い方法を解説します。さらに、タイムカードと勤怠管理システムの違いや、それぞれの適した職場環境についても詳しく紹介します。
勤怠管理の方法や、タイムカードと勤怠管理システムのどちらを導入すべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
❖ タイムカードとは?目的と仕組み
❖ タイムカードの集計方法
❖ タイムカードを使用するメリット
❖ タイムカードを使用するデメリット・注意点
❖ タイムカードの取扱い
❖ タイムカードとタイムレコーダー、勤怠管理システムの違い
❖ タイムカードと勤怠管理システムの選択に迷ったら
❖ 勤怠管理は「KING OF TIME」へおまかせ!
❖ まとめ
勤怠管理の必要性やメリット、デメリット、おすすめの勤怠管理システムについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
タイムカードとは?目的と仕組み
タイムカードとは、従業員の出勤・退勤時刻を記録し、労働時間を管理するための手段です。企業はタイムカードの記録をもとに従業員の労働時間を正確に把握し、給与計算や労務管理に活用します。
基本的な仕組みは、従業員が紙製またはカード型のタイムカードを専用機器に挿入し、打刻するというものです。管理者は締め日に1ヵ月分のタイムカードを回収し、新しいタイムカードを配布します。
タイムカードの集計方法

タイムカードといえば、一般的に紙ベースのものを指し、集計は電卓やエクセルを用いた手作業で行ないます。
◇紙ベース
紙製のタイムカードは、多くの企業や店舗で採用されているスタンダードな種類のタイムカードです。専用のタイムレコーダーにカードを挿入し、出退勤時刻を打刻するだけなので、従業員にとって扱いやすいのが特長です。コストも比較的低く、導入しやすい点もメリットといえます。
一方で、集計には手作業が必要となり、計算ミスのリスクがあるほか、企業規模が大きくなるほど時間と手間がかかります。そのため、月末の負担が大きくなる点には注意しなければなりません。
◇エクセル集計
タイムカードの集計には、電卓やエクセルを用います。エクセル集計は、電卓による手計算よりも効率的で精度が高く、関数やテンプレートを使用すれば労働時間の計算を自動化できます。しかし、従業員数が増えるとフォーマットの管理が複雑化し、設定ミスによる計算の誤差が発生しやすいのが難点です。
このほかに、集計機能付きのタイムカードもあります。紙に打刻する仕組みはそのままに、実働時間や残業時間の自動集計と印字ができるタイプです。ただし、タイムレコーダーが対応する集計項目は限られており、特殊な勤務体系の場合は別途計算する必要があります。
タイムカードを使用するメリット
勤怠管理にタイムカードを用いるメリットは、おもに次の2つです。
◇導入費用が比較的安い
タイムカードによる勤怠管理は、コストが安く、打刻機器のタイムレコーダーと従業員分のカードを用意するだけで運用可能です。また、維持費も用紙代とインク代程度で済みます。
運用にインターネット環境を要しないためサーバー管理費用などもかからず、大きな予算を必要とせずに気軽に導入できる方法といえるでしょう。
◇シンプルな仕組みで使いやすい
タイムカードは、出勤・退勤時にカードをタイムレコーダーに挿入するだけで打刻が完了するため、誰でも簡単に使えます。別途の登録作業なども必要なく、パソコンやシステムに不慣れな従業員が多い職場でも安心して活用できます。
タイムカードを使用するデメリット・注意点

タイムカードで勤怠管理を行なうにあたっては、いくつかのデメリットに注意を払う必要があります。特に気を付けておきたいのは、以下の点です。
◇打刻漏れ・不正打刻や集計ミスが起きるリスクがある
タイムカードは従業員が手動で打刻するため、打刻忘れや時間の記入ミスが発生しがちです。タイムカードを打刻したのが誰か判別する仕組みがなく、代理打刻などの不正が発生するリスクも考えられます。実際の勤務時間と記録が異なれば、正確な勤怠管理はできません。
また、手作業での集計でミスが生じると、給与計算に影響をおよぼすこともあるでしょう。特に残業時間の集計漏れが起こると、実労働時間と給与にズレが生じ、未払いがあれば法令違反となる可能性もあります。細かな確認作業が不可欠ですが、手作業では時間がかかり、業務負担は増すばかりです。従業員との信頼関係を損なわないためにも、効率よく正確に記録できる仕組みを備えなければなりません。
◇長時間労働や残業などをリアルタイムに把握できない
紙のタイムカードは月末に集計するのが一般的であり、従業員の勤務状況をリアルタイムで確認できません。そのため、長時間労働や過重労働の発生を管理者が速やかに把握できず、労務リスクが高まります。
労働基準法の改正により、労働時間を適切に管理する義務が強化されていますが、タイムカードでは迅速な対応が難しいのが実情です。特に、働き方改革の推進にともない、労働時間の正確な把握が求められているため、適切な勤怠管理方法を検討する必要があります。
◇リモートワークに対応できない
紙のタイムカードはオフィスや店舗など決められた場所での打刻を前提とするため、リモートワークや出張時の勤怠管理には対応できません。近年導入が進む在宅勤務においても、タイムカードでは勤務時間を正確に記録できず、実際の労働状況を把握しにくいことが問題です。
そこで、リモートワークを推進する企業では、クラウド型の勤怠管理システムやGPS打刻を活用するケースが増えています。従業員の多様な働き方に対応するためにも、柔軟な勤怠管理の仕組みを検討する必要があるでしょう。
◇保管スペースやコストが必要になる
紙媒体のタイムカードは長期的な保管が必要であるため、管理の手間やスペースの確保が課題となります。労働基準法により、企業はタイムカードを当分の間3年は保存する義務があり、特に従業員数が多い企業では大量の書類を管理しなければなりません。
また、エリアマネージャーや本社の管理者が従業員の労働時間を確認する際、いちいちタイムカードのある現場に足を運ばなければならず、非効率です。さらに、紙代やインク代などのランニングコストも発生し、デジタル管理と比べて長期的なコスト負担が大きくなる点もデメリットの一つです。
参考:労働基準法第109条
タイムカードの取扱い
続いて、タイムカードを押すタイミングや機器の設置場所など、適切な管理の仕方についてのポイントを解説します。
◇設置する場所
タイムカードは、従業員が確実に打刻できるよう、出入り口付近や受付など必ず通る場所に設置するのが基本です。設置場所が不適切だと打刻漏れが発生しやすく、正確な勤怠管理が難しくなります。
また、人目につかない場所に設置すると不正打刻のリスクが高まる一方、人通りが多すぎる場所に設置すると業務の妨げになる可能性があるため、適切な設置位置を吟味することが重要です。
◇押す(読み取る)タイミング
タイムカードは、出勤時と退勤時に打刻するのが原則です。これにより、労働時間の正確な記録が可能になります。なお、休憩時間の打刻は法律上求められていません。ただし、休憩取得の確認やより正確な勤務管理のため、企業の方針によっては記録を求めることもあります。
遅刻や早退が発生した際にも正確なデータを残すため、従業員へのルール周知を徹底することが重要です。打刻タイミングを明確にすることで、隠れ残業などの問題を防ぎ、正しい勤怠管理につなげられます。
◇使用後の保管
タイムカードは、労働基準法に基づき当分の間3年の保存が義務付けられています。紙のタイムカードは月ごとや年ごとにファイリングし、鍵のかかるキャビネットや専用の保管室で管理するのが望ましいところです。
一方、データで保存する場合は、バックアップを定期的に取得し、紛失や改ざんのリスクを防ぐことが重要です。デジタル管理をすることで、過去の記録を迅速に検索でき、労働基準監督署からの提出要請にもスムーズに対応できます。
タイムカードとタイムレコーダー、勤怠管理システムの違い
タイムカードと、タイムレコーダーや勤怠管理システムとの違いを整理します。
◇タイムカードとタイムレコーダーの違い
タイムレコーダーとは、従業員の出退勤時刻を記録するための機器であり、タイムカードはその機器に挿入して打刻する媒体そのものを指します。タイムレコーダーの使用により正確な時刻が記録され、手書きする場合と比べて勤怠管理の精度向上が可能です。
タイムレコーダーとタイムカードは基本的にセットであり、両者を合わせて「タイムカード」と言い表す場合もあります。
◇タイムカードと勤怠管理システムの違い
タイムカードは紙のカードを使い、出退勤時刻を記録する方法です。
これに対して、勤怠管理システムはパソコンなどの電子機器およびネットワークを使用します。また、勤怠情報の記録だけでなく、労働時間の自動計算や休暇管理、シフト調整など、労働管理全般ができる点に特長があります。
勤怠管理システムの導入により、パソコンやスマートフォンからの打刻が可能となり、リモートワークやフレックスタイム制にも柔軟に対応できます。クラウド型システムを導入すれば、リアルタイムで勤務状況を確認でき、給与計算ソフトと連携することも可能です。
タイムカードと勤怠管理システムの選択に迷ったら
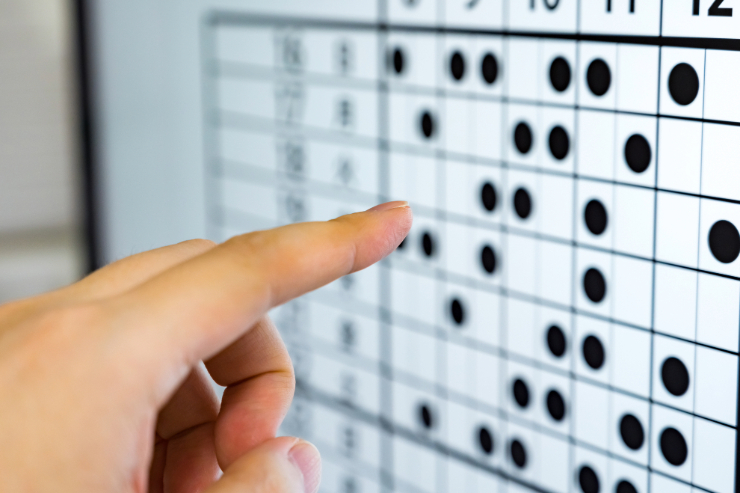
勤怠管理を効率良く行なうためには、タイムカードと勤怠管理システムのどちらを導入すればよいのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを理解し、適切なシステムを選ぶ必要があります。
タイムカードは、少人数(最大でも50人程度)の職場や定時勤務の職場、ITに不慣れな従業員が多い職場に適しています。しかし、打刻漏れや手作業での集計ミスが発生しやすく、勤務状況の確認に時間がかかる点はデメリットです。働き方が多様化するなかで、リアルタイムでの労働時間管理や柔軟なシフト調整が求められ、勤怠管理システムへ移行するケースが増えています。
◇勤怠管理システムでできること
勤怠管理システムは、出退勤の記録だけでなく、労働時間の管理や給与計算、シフト・休暇の申請と承認など、多くの業務を一元化できます。特に、残業時間のリアルタイム集計やアラート機能は、長時間労働の防止にも役立ちます。
シフト管理機能を活用すれば、従業員の希望シフトの収集や調整をスムーズに行なうことが可能です。また、給与計算ソフトと連携することで、手入力の手間やミスを削減できます。さらに、リモートワークやフレックスタイム制にも対応できるなど、多様な働き方に合わせた管理も容易です。
◇勤怠管理システムへ移行する際のポイント
勤怠管理システムの導入に際しては、自社の業務形態やニーズに適したシステムを選ぶことが重要です。まず、ネットワークを介するクラウド型か、自社ネットワークにのみ限定するオンプレミス型かを検討し、ほかの業務システムと連携できるかも確認しましょう。特に、給与計算ソフトや労務管理システムと連携できるかどうかは、業務の効率化に直結します。
また、システムのカスタマイズ性やサポート体制が整っているかも重要なチェックポイントです。セキュリティ対策やランニングコストを考慮し、従業員数や勤務形態に合ったシステムを選ぶことで、よりスムーズな移行と運用が可能になります。
勤怠管理は「KING OF TIME」へおまかせ!
「KING OF TIME」は、クラウド型の勤怠管理システムで、あらゆる勤務形態に対応できる柔軟性が特長です。ICカードやスマートフォン、パソコン、生体認証など、多様な打刻方法を選べて、職場環境に合わせた最適な運用が叶います。
また、自動集計により給与計算の負担を軽減し、リアルタイムで労働時間を把握できるため、過重労働対策にも有効です。さらに、変形労働制やフレックスタイム制にも対応。KING OF TIMEなら、勤怠管理だけでなく人事・給与管理まで一括して行なえて、業務の効率化を強力にサポートします。
■ 無料トライアルのお申し込みはこちら >>>
■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>
まとめ
タイムカードは導入コストが低く、使いやすいというメリットがある一方で、手作業での集計ミスや不正打刻のリスク、長時間労働のリアルタイム管理が難しい点が課題です。一方、勤怠管理システムは自動集計やシフト管理が可能で、多様な働き方に対応できます。
企業の規模や業務形態に応じて、適切な勤怠管理方法を選ぶことが重要です。効率的な勤怠管理を実現するために、タイムカードと勤怠管理システムの特性を理解し、自社に最適な方法を導入しましょう。
「KING OF TIME」は、専門知識がなくても扱いやすい勤怠管理システムです。初期費用0円で導入でき、専門スタッフのサポートも充実しています。勤怠管理をスムーズに進めたい方は、ぜひ無料トライアルをご活用ください。








