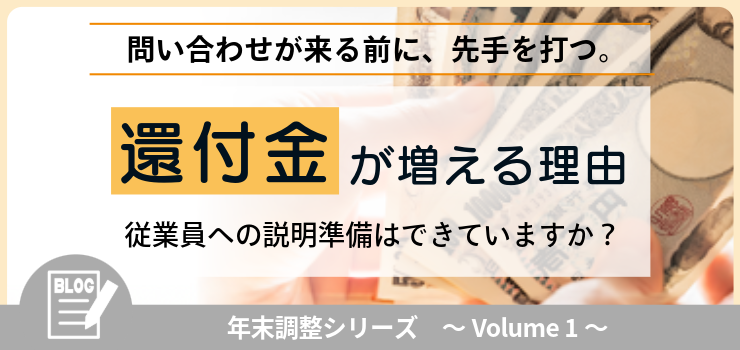
本特集のピックアップ
◆ 概要
◆ 本シリーズブログのゴールと心得
◆ 2025年税制改正の主なポイント
◆ 実務上の注意点と事前準備
◆ 年末調整の電子化の動向
はじめに
2025年8月6日と9月4日に、ヒューマンテクノロジーズ主催で「KING OF TIMEユーザー様必聴! 2025年、年末調整の法改正ポイントは?実務対応を踏まえて先取り!!」というセミナーを実施しました。
当日は、税理士法人総合経営サービス代表社員である中川祥瑛(なかがわ・しょうえい)先生にご登壇いただき、「今年の年末調整における税制改正の要点」や「『年収の壁(税制改正)』の変化と実務への影響」「電子化が進む年末調整の現状」などをご解説いただきました。
参加者の皆様からは「年末調整の準備ができた」「実務に役立つ」といったお声を多数いただき、大きな反響を実感しております。また、残念ながらご参加いただけなかった方からも多くのお問い合わせをいただきました。
そこで、参加できなかった方にも当日の内容をお届けしたく、急遽全3回にわたるレポートを公開することにいたしました。ぜひ、今後の実務にお役立てください。
今回はその1回目です。
●第2回
【要注意】お子様のアルバイト収入、「103万円の壁」の認識はもう古いかもしれません。
●第3回
従業員のマイナンバーカード、眠らせていませんか?スマホひとつで申請が終わる、これからの常識
●第1回
問い合わせが来る前に、先手を打つ。『還付額が増える理由』、従業員への説明準備はできていますか?
概要
今回のシリーズブログは「2025年年末調整の実務対応」をテーマに解説いたします。
ご存知のとおり、今年の年末調整における最大のポイントは、いわゆる「年収の壁」問題への対応です。幸い、この点以外に大きな制度変更はありません。
そこで、まず年末調整の基本的な仕組みを皆様と再確認し、そのうえで今回の法改正の要点を重点的にご説明します。この2点を押さえることで、今年の年末調整にも落ち着いてご対応いただけると考えております。
最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。
本シリーズブログのゴールと心得
本シリーズブログのゴールは「2025年税制改正を踏まえた年末調整のポイントと具体的な対応策」を理解することです(注:本シリーズブログは全3回を通じてのゴールとなります)。
実務上、最も注意すべき点は、「毎月の給与計算」と「年末調整」とでは適用されるルールが異なるという点にあります。2025年11月までの給与計算は、現行の法律に基づいて行われます。しかし、年末調整の際には、扶養控除の拡大など改正後の法律を反映させる必要があります。
その結果、どうなるのでしょうか。毎月の源泉徴収税額はこれまでどおりですが、年末調整で計算する控除額は大きくなります。これは、年間を通じて見ると税金が過大に徴収されている状態となり、年末調整での還付額が例年より大きくなる可能性が高いことを意味します。
この仕組みは、2024年の定額減税とは逆のパターンです。定額減税では、毎月の控除額が大きかったために、年末調整で追加納付が発生する、つまり還付額が少なくなるケースが多く見られました。
しかし、今回の法改正はそれとは逆に「多くの方にとって還付額が大きくなる内容である」とご理解いただければと思います。
2025年税制改正の主なポイント
2025年の改正ポイントを整理すると、「基礎控除の見直し」と「扶養親族要件の変更」が主なポイントです。
まず「基礎控除の見直し」ですが、2025年の年末調整から基礎控除は所得に応じた段階制になります。基礎控除額は、かつて38万円から48万円に引き上げられましたが、今回の改正でさらに所得に応じた段階制となり、最大で95万円になります。特に高所得者への影響が大きくなる改正です。
次に「扶養親族要件の変更」です。扶養親族の合計所得金額の要件が、従来の48万円から58万円に変更されます。この改正は多くのご家庭に影響をもたらすでしょう。これまで扶養の条件は、給与収入が103万円以下であることが一般的でした。今回の改正では、この「103万円の壁」が段階的に見直されているのがポイントです。
加えて、大学生などを対象とした「特定扶養親族」の扱いに新しい仕組みが導入されました。これまでは収入が103万円を超えると扶養から外れていましたが、大学生の4年間は、一定の所得があっても引き続き扶養の対象とできるようになります。
これらの改正により、これまでの「扶養は103万円以下」といった大まかな認識では対応が難しくなります。年末調整システムの設定更新や、手計算で業務を行う場合は、特に基礎控除と扶養親族要件の正しい理解が不可欠です。事前の準備と確認を怠ると、計算ミスにつながる可能性があるため注意しましょう。
実務上の注意点と事前準備
今回の改正を受けて、年末調整の担当者の皆様は何を準備すべきでしょうか。重要なのは、実務への影響を正しく理解し、今のうちから具体的な対応策を検討しておくことです。
まず、控除額の変動について、社内への事前通知を強くお勧めします。先ほど申し上げたとおり、2025年中の給与計算と年末調整とでは、適用されるルールが異なります。その結果、多くの従業員の方にとって還付額が例年より大きくなると予想されます。
還付額が増えること自体は歓迎されますが、「なぜ今年はこんなに多いのか?」という疑問は必ず生じます。還付額の急な変動は従業員の方の関心事であり、年末調整の担当者の皆様に問い合わせが集中する可能性は非常に高いでしょう。そこで、「本年は税制改正により、年末調整の還付額が例年より多くなる見込みです」といった内容を事前に社内通知しておくことをお勧めします。この一言があるだけで、個別の問い合わせ対応に費やす時間を大幅に削減でき、業務負担の軽減につながります。
次に、申告書様式の変更にも注意が必要です。年末調整の書類は毎年少しずつ変更されますが、今年は特に注意してください。もし手書きで年末調整を行っている場合、旧様式は絶対に使用しないようにしましょう。
特に、計算の根幹に関わる「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」や「源泉徴収簿」は、大きな変更が予定されています。年末調整業務に着手する前には、国税庁などから発表される最新の様式を必ず確認し、新しいルールで臨むようにしてください。
年末調整の電子化の動向
電子化により業務効率が大幅に向上します。
①年末調整システムの導入
電子化は、書類提出までのプロセスを自動化し、人為的なミスを減らすうえで絶大な効果を発揮します。様々な会社が年末調整システムを提供していますが、近年の主流は、従業員の方による申告から控除証明書の提出までをウェブ上で完結させるものです。これらのシステムを導入する最大の利点は、年末調整の担当者の皆様が従業員の方の書類を預からなくて済む点にあります。
電子化していない場合、従業員の方から提出された書類の内容を、年末調整の担当者の皆様が1件ずつ転記するのが一般的な流れです。電子化した場合、従業員の方が自身の情報や生命保険料の控除情報などをシステムに直接入力します。これにより転記作業が不要となり、従業員の方が入力を終えた時点で年末調整のデータ収集はほぼ完了します。
この利点を踏まえ、年末調整システムの導入は、早期に取り組むべき課題の一つであると考えています。
②年末調整におけるマイナポータルの活用
マイナポータルは従業員の方本人が各種控除証明等のデータを取得・連携できる仕組みで、取得したデータを会社へ提出することで情報収集が効率化します。これを年末調整でどの程度活用するのか、企業として方針を定めておく必要があります。
例えば、法改正により今年から住宅ローンの控除書類がマイナポータルに格納されるようになりました。もちろん、これまでどおり紙の書類で手続きすることも可能ですが、マイナポータルを活用すれば、銀行や生命保険会社が発行する証明書も電子データとして集約し、企業のシステムに直接反映させることも可能になってきています。
年末調整の担当者の皆様は、自社の年末調整の方向性を今のうちから固めておくことが重要です。9月から10月頃には関連システムのアップデートも行われ、具体的な進め方が決まってきます。その際に慌てないよう、「電子化」で進めるのか、「従来どおり」の方法でいくのか、大枠の方針は決めておくとよいでしょう。
電子化を選択する際には、従業員の方側の準備も不可欠です。各自が自身のマイナポータルへ必要な電子情報を格納する必要があるため、その準備を促すための情報発信が企業に求められます。社内で誰がその役割を担うのかも、今のうちに決めておかなければなりません。
電子化の仕上げとなるのが、国税の「e-Tax」と地方税の「eLTAX」の導入です。すでにご利用の企業も多いかと思います。e-Taxは国税の電子システムです。年末調整の場面では、算出された源泉所得税を納付する際に活用できます。毎月納付や半期ごとの納付といった企業の形態にかかわらず、銀行と連携させることで、窓口に出向くことなく電子納税(自動引落とし)が可能になるのが特徴です。
一方のeLTAXは地方税の電子システムで、主に住民税の納付に利用されます。こちらも同様に、電子データを用いた引落としによる納税が可能です。これらにより、銀行窓口で納税するといった手間を削減することができます。こうした利点があるため、e-TaxやeLTAXを導入する企業は着実に増えています。
このように、年末調整をめぐる環境は、従来の紙ベースの業務から電子化へと大きく移行しています。具体的には、従業員の方はマイナポータルで自身のデータを集約し、システム上で情報を入力します。一方、企業はe-Tax・eLTAXで納税を電子化(自動引落とし)するという流れが主流になりつつあるのです。紙の書類や納付書を前提とした手続きからデジタルで完結する形へと、年末調整のあり方は大きく変化しています。この現状は、年末調整の担当者の皆様が確実に把握しておくべき重要な動向と言えるでしょう。
●第2回
【要注意】お子様のアルバイト収入、「103万円の壁」の認識はもう古いかもしれません。
セミナー講師紹介
税理士法人総合経営サービス 代表社員
一般社団法人中小企業成長支援センター代表理事
一般社団法人ライフデザイン協会代表理事
中川 祥瑛(なかがわ しょうえい)氏

石川県出身。法人・個人問わず決算・申告の最終チェックを担当し、節税・税務調査・相続対策に従事。現在は総合経営サービスグループ税理士法人の税務部門長を務め、セミナー講師も担当。経理業務のクラウド化・電子化などバックオフィス改善を推進し、枠にとらわれないサービスを提供。人材育成にも注力し、所内研修講師として累計1000回以上登壇している。
【著書】『病医院のための税理士の選び方がわかる本』
『小さな会社の給与計算と社会保険24-25年版』
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








