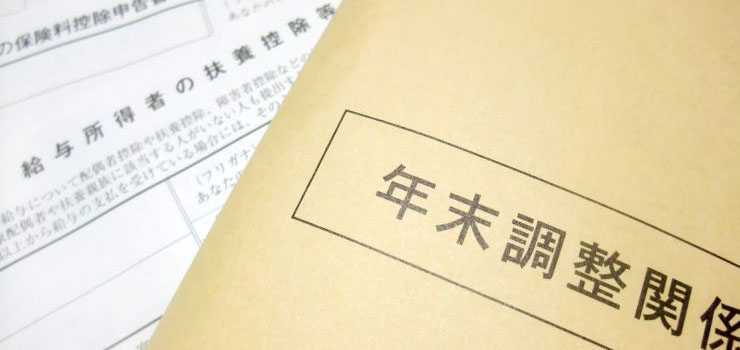
年末調整は、会社員にとって毎年恒例の業務です。しかし所得税に関する重要な手続きであるにもかかわらず、実施する理由を正確に理解していない方は少なくありません。
そこで本記事では、年末調整の基本的な仕組みや目的をはじめ、源泉徴収や確定申告との違い、必要書類や手続きの流れまで、労務担当者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
❖ 年末調整とは?概要と目的
❖ 年末調整の対象者
❖ 年末調整と源泉徴収・確定申告の違い
❖ 年末調整で従業員に提出してもらう書類
❖ 年間の所得税額の計算
❖ 年末調整で適用されるおもな控除
❖ 年末調整計算後の各種書類提出処理
❖ 年末調整で申告書を提出しないとどうなる?
❖ 2025年最新の年末調整のおもな変更点
❖ 年末調整のデータ確認や計算も「KING OF TIME」におまかせ
❖ まとめ
年末調整とは?概要と目的
年末調整とは、最終的な年税額を年末に計算し、精算する手続きのことです。
通常、社員が納付する所得税は、毎月の給与や臨時の賞与などを支給するたびに、そこから控除(源泉徴収)されています。ただし、「扶養する家族に異動があった」場合や、「生命保険料や地震保険料などの所得控除がある」などの理由により、毎月の給与控除額の合計と本来の年税額が一致しないケースが多くあります。
そこで、1月から12月までの1年分の収入が確定した時点で正確な所得税額を計算し、これまでの納付税額との過不足を精算する手続きを行う必要があるのです。これが、「年末調整」です。
この年末調整は、源泉徴収義務者である会社に実施が義務付けられており、年末調整を実施したあとは、税務署や社員が居住する市区町村にその内容を報告する必要があります。
年末調整の対象者
年末調整は、すべての人が対象となるわけではありません。会社などに勤めている給与所得者のうち、一定の条件を満たす人が対象です。対象外のケースと併せて詳しく見ていきましょう。
◇ 対象となる人
年末調整は、会社などに勤めていて給与から源泉徴収が行われており、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人が対象です。
基本的には、1年を通じて同じ勤務先で働いている人が対象ですが、次のようなケースも含まれます。
• 年の途中で就職または転職し、年末まで勤務している人
• 年の途中で退職した人
• 海外勤務などで非居住者となった人
また、所得面でも条件があります。
• 年間の給与収入が2,000万円以下
• 給与以外に大きな副収入(雑所得や事業所得など)がない
• 扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など、何らかの所得控除を受けている
さらに、心身の障害により退職し12月31日までに再就職の見込みがない人や、年の途中で亡くなられた人も対象です。なお、雇用形態に関係なく、条件を満たしていれば、正社員に限らずパートやアルバイトの人も年末調整の対象となります。
◇ 対象とならない人
一方で、次のような人は年末調整の対象外となり、自身で確定申告を行う必要があります。
• 自営業者やフリーランスなど、給与以外の収入で生計を立てている人
• 1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える人
• 給与以外に多額の副収入がある人
• 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
• 2か所以上から給与の支払を受けている人で、ほかの給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
• 年の中途で退職した人(年末調整の対象とならない事由に該当する場合)
• 非居住者
• 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者
年末調整と源泉徴収・確定申告の違い

年末調整の前段階には源泉徴収がありますが、具体的にはどう違うのでしょうか。
また、同じく所得税を報告する確定申告との違いは何でしょうか。
併せて解説します。
◇ 源泉徴収とは?年末調整との違い
日本では給与支払の際に、支払者である会社がその支払金額から所得税を徴収して、国に納付する「源泉徴収制度」が採用されています。
会社は給与や賞与から都度、所得税を源泉徴収し、従業員の代わりに納めているのです。
年末調整では、月々の給与から源泉徴収した所得税額と、控除を反映させた正確な所得税額の差額を年末に計算し、徴収、または還付します。
また、年末調整により最終的に確定したその年の所得税額を源泉徴収額といいます。
もともと源泉徴収制度は、昭和15年の税制改正で、納税の簡易化、納税者の把捉などを目的に所得税に導入されました。その後、戦後の税制改革で、国民全員が確定申告をする負担を軽減するために年末調整制度が採用されました。
このように課税対象者がすべて確定申告を行うと、税務署の事務混雑や申告忘れなどが発生する恐れがあることから、会社が年末調整により正しい年税額を計算したうえで、その内容を税務署へ報告するようになったという経緯があります。
一般的に給与所得者は、勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどのため、勤務先で年末調整を行うことで、その年の納税が完了し、確定申告は不要となっています。
◇ 確定申告とは?年末調整との違い
年末調整と確定申告は、どちらも1年間の所得に対する税金を精算する手続きですが、対象者や手続き方法が異なります。
まず、年末調整は会社が行うもので、従業員に代わって所得税の過不足を年末に調整する仕組みです。
従業員は必要な書類の提出を求められますが、自分で手続きする必要は基本的にありません。
一方、確定申告では、1年間の所得や税額の計算、および税務署への申告を自分で行う必要があります。また、おもな対象者は、個人事業主や年金受給者、副業による収入がある会社員などです。
会社員の多くは年末調整、自営業者などは確定申告というのが一般的な使い分けで、所得税の納付や還付のために実施します。
年末調整で従業員に提出してもらう書類

年末調整を行うにあたって、社員からは以下の書類を提出してもらいます。
◇ 1. 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
扶養の有無にかかわらず、年末調整を行うすべての従業員が会社へ提出する必要のある書類です。
右上部に丸囲みの「扶」の字が印字されているため、通称「マル扶」とも呼ばれます。
控除対象となる扶養者がいる場合は、扶養控除や障害者控除など、その対象や人数に応じた控除を受けられます。2016年からは申告書へのマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりましたが、会社側でマイナンバーを記載した帳簿を作成しているときには省略可能です。
◇ 2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
この申告書も、ほぼすべての給与所得者が対象となる書類です。
基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除を申告するために使用します。
令和2年からこの様式となり、3つの申告書(基礎控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除)が兼ねられたものとなりました。
◇ 3. 給与所得者の保険料控除申告書
その年に支払った生命保険料や地震保険料等の控除を受けるために、会社へ提出が必要な書類です。
すなわち、その年に対象保険料を支払った人が提出の対象です。
右上部に丸囲みの「保」の字が印字されているため、通称「マル保」とも呼ばれます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金なども、この書類で申告を行います。
申告には、保険会社などから送付される「控除証明書」の添付が必要です。
なお、毎月の給与から控除される健康保険料や介護保険料は記入する必要がありません。
◇ 4. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除や住宅ローン減税を受けるために会社への提出が必要な書類です。
個人が住宅ローンなどを利用して、マイホームを購入した場合に、この書類で申告を行います。
住宅ローン控除を受ける最初の年は自分で確定申告をする必要があるため、2年目以降に該当する給与所得者が対象です。
申告には、住宅ローンを利用している金融機関が交付した、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高を証明する書類の提出が必要です。
なお、近年話題になることも多い「ふるさと納税」については、年末調整では所得控除を実施できないため、別途ご自身での手続きが必要となります。
年間の所得税額の計算
具体的な計算方法の詳細は割愛しますが、所得税額は下記のようなステップで計算します。
(1)1年間の給与・賞与の支給額から課税総支給額を計算
(2)給与所得控除後の給与等の金額を計算
(3)所得控除額の計算(各申告書に記載されている内容に基づき控除額を確定)
(4)課税所得金額の計算
(5)所得税額の計算(住宅借入金等特別控除がある場合は差引きした額)
年末調整で適用されるおもな控除
年末調整では、所得税にかかる控除額を確定、反映させ、納付済(源泉徴収済)の所得税との差異を算出します。
年末調整を行うときに必要なおもな控除の内容についても押さえておきましょう。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に適用。 所得に応じて控除額は変わる。 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得が48万円以下の場合、最大38万円控除。 納税者の所得に応じて控除額は変わる。 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合に適用。 配偶者・納税者双方の所得に応じて控除額は変わる。 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がおり、所得が48万円以下の場合に適用。 |
| 寡婦控除 | 寡婦であり、かつ所得が500万円以下の場合に適用。 |
| ひとり親控除 | シングルマザー・シングルファザーで、かつ所得が500万円以下の場合に適用。 |
| 勤労学生控除 | 給与所得などが75万円以下、特定の学校へ通う生徒であるなど、一定条件を満たす勤労学生に適用。 |
| 障害者控除 | 納税者本人または同一生計の配偶者・扶養親族が障害者の場合に適用。 |
| 社会保険料控除 | 健康保険料・国民年金・厚生年金などについて、支払った全額を控除。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料について、一定額を上限に控除。 |
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料(旧長期損害保険を含む)について、一定額を上限に控除。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoや小規模企業共済などの掛金について、支払った全額を控除。 |
| 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | 住宅ローンを組んで要件を満たす住宅を取得した人を対象に、一定額を控除(年末調整での控除は2年目以降)。 |
年末調整計算後の各種書類提出処理
年末調整所得や所得税額を確定させたあとは、従業員、税務署、そして市区町村へ、それぞれ必要な書類を作成し提出します。
◇ 1. 源泉徴収票の交付と源泉所得税の納付
年末調整が終わったら、源泉徴収票を従業員に交付します。
年末調整で過不足を清算したあとは所得税を納付します。
過納税額となった場合は、充当(または還付)となります。
◇ 2. 税務署に源泉徴収票と法定調書合計表を提出
管轄税務署に「給与所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出します。提出期限は1月31日です。
◇ 3. 市区町村に給与支払報告書と総括表を提出
住民税を算出するため、翌年1月1日に従業員が居住する市区町村に対して、「給与支払報告書(総括表)」と「給与支払報告書」を提出します。提出期限は1月31日です。
年末調整で申告書を提出しないとどうなる?

年末調整で必要な申告書を提出しなかったり、記入漏れがあったりすると、所得税や住民税にさまざまな影響が生じます。
ここでは、その具体的なリスクと対応について解説します。
◇ 所得税の各種控除が受けられない
申告書を提出しないと、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除などの各種控除が適用されません。
控除が適用されないと課税対象となる所得が増加し、本来よりも多くの所得税を納めることになってしまいます。
従業員には自身が当てはまる控除についての確認や、書類への記入漏れがないよう促しましょう。
◇ 翌年の住民税に影響が出る
所得額は、翌年の住民税算出の基礎に使用されます。
年末調整で各種控除を適切に申告できていないと所得額が多くなり、住民税額が本来より高くなってしまいかねません。
意図せず従業員の経済的負担が重くなるため、注意が必要です。
◇ 納めすぎた所得税の還付が受けられない
納める金額だけでなく、税額還付にも影響する可能性があります。
年末調整では、すでに納付済の税額と、各種控除を加味した本来納めるべき税額との誤差を算出し、納めすぎていた分は還付されます。
しかし、控除が適切に申告されていなければ自動では戻ってきません。
◇ 自分で確定申告や還付申告をしなければならない
年末調整を行えなかった場合は、従業員自身が確定申告する必要があります。
もし確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば還付申告が可能ですが、手続きの手間はかかります。
年末調整後のフォローをどこまで、またいつまで実施するかは企業側に委ねられますが、従業員が相談しやすい環境を整える必要があるでしょう。
2025年最新の年末調整のおもな変更点
年末調整の処理には控除を中心にさまざまな法令が関係しますが、法改正によって変更点が生じる場合があります。正確に年末調整を行うには直近の変更点をしっかりと確認し、法令を遵守しながら適切に所得額および税額を算出することが大切です。
2025年最新のおもな変更点は以下のとおりです。
| おもな変更点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 基礎控除額引き上げ | 合計所得金額132万円以下の場合は基礎控除95万円になる(改正前48万円)。 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円から65万円に引き上げられる。 |
| 特定親族特別控除の新設 | 19歳以上23歳未満の特定親族を扶養すると、一人につき最大63万円の控除が受けられる。 |
| 扶養控除等の対象となる扶養親族等の合計所得金額引き上げ | 改正前の48万円以下から58万円以下に引き上げられる。 |
| 「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書様式変更 | 前年と内容に変更がない場合、変更がない旨の記載のみで申告できるようになる。 |
| 定額減税の取り扱い | 2024年6月開始の定額減税は、年末調整時に年調減税として組み込む必要がある。 所得1,805万円以下を対象に一人当たり3万円の減税が適用される。 |
年末調整のデータ確認や計算も「KING OF TIME」におまかせ
年末調整の作業効率化には、勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME」の活用がおすすめです。
申告書の提出状況や進捗をリアルタイムで把握できる機能が備わっており、対応漏れを防ぐのに役立ちます。また、申告内容に基づいて控除額や税額を自動で計算できるため、手作業による計算ミスや負担を大幅に軽減できるでしょう。
さらに、源泉徴収票や帳票の出力、エラーの確認まで一括してシステム内で完結できる点も大きな魅力です。これにより、年末調整業務全体の効率が大きく向上します。
「KING OF TIME」は、上記のような人事労務・勤怠管理・給与計算・データ分析などの全機能を月額一人当たり300円で利用でき、給与計算機能にも対応しているため、コストパフォーマンスの面でも優れた選択肢といえます。
30日間の無料体験を実施しているため、実際に使用したうえで導入を検討することも可能です。
■ 無料トライアルのお申し込みはこちら >>>
■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>
まとめ
年末調整は、給与所得者の1年分の税額を年末に精算する制度であり、本人が確定申告を行わなくてもよいよう、会社が代わって処理する仕組みです。
必要な書類には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などがあります。
基礎控除は従業員の所得に応じて金額が変動するため、記載内容の確認が重要です。
また、基礎控除額の改正など、年末調整を取り巻く制度は年々変化しています。
制度変更にスムーズに対応できるよう、給与計算や勤怠管理のシステムを活用し、年末調整業務の効率化を検討されてみてはいかがでしょうか。








