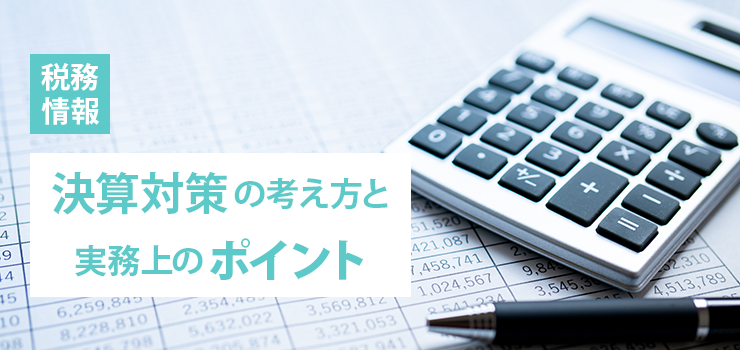
今週のピックアップ
◆ 決算対策と言えば?
◆ 決算月前の対策が重要!
◆ 課税繰り延べの注意点は?
◆ ベストは金銭の支出を伴わない対策
◆ 金銭の支払いを伴う対策は要否に注意
◆ 改めて決算対策の必要性と別の視点
◆ 付加価値のある対策も検討
決算対策と言えば?
総合経営サービスの植松です。
今回は、「決算対策」についてです。
「決算対策」と言えば、かつては、全損型の保険加入で一気に何千万円もの経費を計上するような、インパクトの大きい手法が存在しました。しかし今では、このような方法は税制改正や規制強化により、ほぼ無くなったといっても過言ではないでしょう。
たとえば、現在多くの保険商品では、保険料のうち損金算入できるのは40%に留まり、残り60%は資産計上となります。そのため、仮に1,000万円の保険料を支払っても、400万円しか経費にならず、決算対策としての効果は限定的です。また、解約返戻率の上限も85%程度とされており、返戻金の魅力も相対的に低下しています。
今後、新たな保険商品が登場する可能性もありますが、効果が高ければ再び規制の対象となることが予想されます。このように、制度改正とのいたちごっこのような状況が続いています。もちろん、リスクへの備えや資産運用という本来の目的で保険に加入すること自体は重要です。 必要な保障額があるかどうかなど、目的に応じて判断することが重要です。
決算月前の対策が重要!
決算対策で最も重要なのは、決算月より前に着手することです。
決算月を過ぎてからではできる対策は限られ、十分な効果が得られません。例えば、物品の購入や契約の締結は、決算月を過ぎると翌期の費用として処理され、当期の経費にはなりません。予測を立てながら、計画的に行うのがよいでしょう。
課税繰り延べの注意点は?
決算対策としては、一般的に課税の繰り延べがよく用いられます。
典型的な例としては、保険契約やオペレーティングリース(船舶・航空機等)などが挙げられます。
しかし、これらは複数年にわたって大きな支出が必要となり、契約期間中の資金繰りをしっかり確認しておかなければなりません。
また、満期や解約のタイミングでは多額の利益が発生するため、役員退職金などの支払いとタイミングを合わせるのが一般的ですが、中小企業では、予定どおりに役員が退任できないことも多く、タイミングがずれれば効果は限定的です。つまり、繰り延べた意味がほぼなくなることも起こりうるということです。
そのため、金額の大きな対策や長期にわたる対策は、特に慎重に検討する必要があります。
ベストは金銭の支出を伴わない対策
決算対策においては、金銭の支払いが無いものがベストだと考えています。そのうえで効果的な対策としては、貸借対照表の資産項目の見直しがあります。
まずは、以下のような点をチェックし、該当するものがあれば、それぞれ対策を講じていきます。
■ チェックポイント
① 固定資産や棚卸資産等で、もう使わないものはないか?
② 有価証券等の投資をしている場合には、評価損が大きくなっているものはないか?
③ 売掛金等で回収が見込めないものはないか? etc
■ 対策と効果
① 使用予定のない固定資産を廃棄する。
これにより、帳簿価額分を損金計上できる場合があります。
② 評価損が出ている有価証券を売却する。
これにより、売却損を計上できます。
③ 売掛金等で回収が見込めないものは、債権放棄する。
これにより、経費にできる可能性があります。ただし、貸倒処理には厳格な要件があります。
また、中には例外的に決算月の後で計上することができるものもありますが、これらについては、顧問税理士等の専門家に相談してください。
金銭の支払いを伴う対策は要否に注意
決算対策に合わせ、必要なものを購入するのも良いでしょう。一方で、そこまで必要の無いものを購入するケースも見受けられますが、決算対策のためだけに不要な支出を行うのは考えものです。さらに、通常よりも多くの消耗品を購入した場合、貯蔵品として資産計上が必要になる場合ありますので注意してください。
■ 金銭の支払いを伴う対策例
・自動引き落とし経費の未払計上
・中小企業倒産防止共済制度への加入(1年分の前払いも可能)
・日当等の社内規定整備 etc
改めて決算対策の必要性と別の視点
決算対策と聞くと「何かお金を使わないといけない」「利益を減らさないといけない」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、利益が出ることは悪いとか必ずしも損ということではありません。
改めて、原点に立ち戻って考えてみると、まず、会社は利益を出してこそ継続できるものです。とくに借入金がある場合は、利益がなければ返済できず、資金繰りが悪化してしまいます。
手元にお金を残すという観点では、決算対策をしない方が結果的にお金が残ります。たとえば、100万円の支出で減る税金は約30万円程度です。つまり、支出をしなければ税金は増えるものの、70万円は手元に残ります。
もちろん、必要な備品・設備の購入やリスクヘッジ等のための保険加入は有効であり、すべきものもあります。しかし、無理な決算対策は、続かなかったり、翌期以降の経営に悪影響を与えるリスクもあるため、やめた方が良いということです。
付加価値のある対策も検討
最近では、決算対策で税金を減らすというよりも、余剰預金があるのであれば、それを従業員に投資する、利益を増やし納税が増えても手元に預貯金またはすぐに預貯金になるものを増やしていくという考え方を採用する会社も増えてきています。
そのような会社にお勧めなものの1つとして、「企業型確定拠出年金(日本版401k)」があります。
企業型確定拠出年金とは、年金制度の1つで、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用するものです。すでに取り入れている会社もあると思いますが、これは会社のみならず従業員にもいろいろとメリットがあります。
税や社会保険料に関して、掛金は会社にとって経費として扱われ、報酬とはみなされないため、社会保険料の負担が軽減されます。従業員にとっても会社から掛金を拠出してもらっても、それに対しては税や社会保険料がかかりません。さらに運用益も非課税で、老後資金として受け取れます。
従業員の満足度や定着率を向上や採用において求職者の関心を促すことを目的に、福利厚生の一環として取り入れる企業も増えています。
また、退職金制度の代替という観点でも、企業型確定拠出年金は検討できます。そのため、現在、退職金制度が無い会社や制度を見直したい会社にはお勧めです。
まず、退職金制度がない会社には、従業員の将来の年金不安の一助となりえるでしょう。
問題は、すでに退職金制度がある会社です。なぜかというと、退職金を支払う際にはある程度、まとまったお金が必要です。支払いに備えてお金を積み立てていくにしても、これは経費にできません。
この点、企業型拠出年金では、資金の運用は従業員にまかせられるとともに、会社が拠出する掛金についても税や社会保険料のメリットが得られるため、既存の退職金制度と比べて、資金の準備や支払い、それらを含めた運用の負担軽減が期待できると言えるでしょう。
監修者紹介
税理士法人総合経営サービス 植松 伸
下町生まれの税理士の植松伸です。
税理士になる前は建設系の労働組合で働いていたので、建設業等の許認可や健康保険事務組合の知識もあり、それらの業務を弊社グループ内へつなぐことも大事にしています。
趣味は観賞魚飼育で、現在自宅に水槽が10個あります。
魚を眺めたり、水の音はとてもリラックスできるのですが、水槽の掃除等のメンテナンスに時間がかかるので、ちょっと増やしすぎたと反省する毎日です。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








