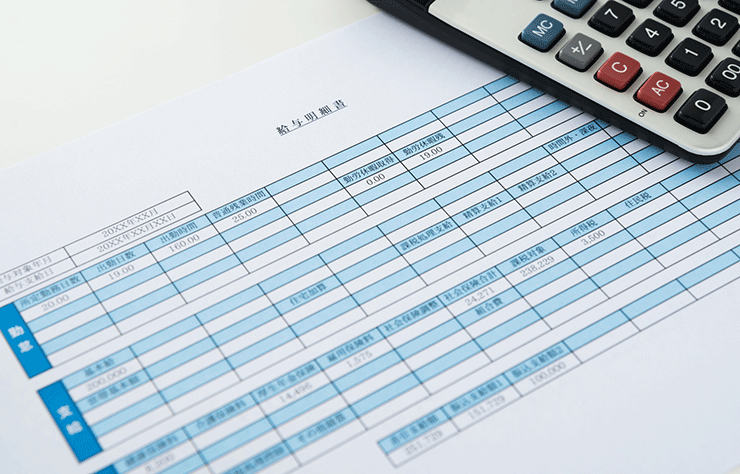
企業には給与明細を適切に発行する義務があり、そこには支給額や控除額、勤怠情報などを明記する必要があります。これらの項目は、従業員側としても理解しておかなければなりません。
本記事では、給与明細の基本的な役割や記載項目の見方、確認すべきポイント、発行方法などについて詳しく解説します。給与計算の透明性を確保し、正しい情報を把握するためにも、給与明細の見方をしっかり理解しておきましょう。
この記事では、以下について解説します。
❖ 給与明細とは?発行の目的
❖ 給与明細に書かれている項目と見方
❖ 控除額とは?何が引かれているのか
❖ 給与明細の取扱いについて問い合わせを受けたら
❖ 雇用形態によって給与明細に違いはある?
❖ 給与明細の発行方法について
❖ 給与管理は「KING OF TIME」へおまかせ!
❖ まとめ
給与明細とは?発行の目的
給与明細とは、従業員が受け取る給与の内訳を記した書類です。企業は所得税法第231条に基づき、給与を支払う際に明細書を交付する義務があります。これにより、給与計算の透明性を確保し、従業員との間で認識のずれを回避できます。給与明細のフォーマットに法的な決まりはありませんが、基本的な項目は共通しており、基本給や各種手当などの支給額、社会保険料や所得税などの控除額ほか詳細が記載されます。
これにより、従業員は実際の手取り額の根拠を把握でき、企業側も勤怠管理や給与計算の適切さを証明する資料として活用可能です。正確な給与明細の発行は、従業員の信頼を維持し、企業の法的義務を果たすうえで不可欠です。
参考:所得税法第231条
給与明細に書かれている項目と見方
給与明細には、大きく分けて次の4つの要素が記載されています。
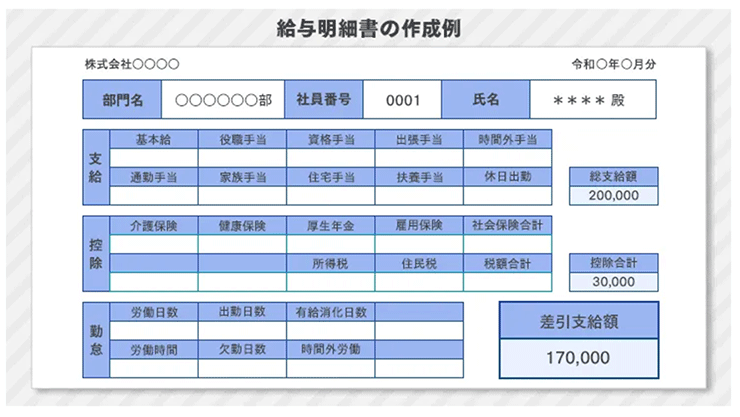
2.控除額:税金や社会保険料など、給与から差し引かれる金額
3.差引支給額:実際に受け取る手取り額
4.勤怠情報:出勤日数や残業時間、有給休暇の取得状況など
給与計算のミスや控除額の誤りを防ぐためにも、企業側、従業員側の双方が正しい見方を知ることが重要です。
◇支給額
支給額は、おもに基本給と各種手当で構成されています。基本給とは、労働契約で定められた基本的な賃金です。また、各種手当には残業手当や通勤手当、住宅手当などが挙げられます。
<手当の例>
・残業手当:所定労働時間を超えた労働に対する手当
・通勤手当:交通費の補助(非課税枠あり)
・住宅手当:家賃やローンの補助
・役職手当:役職に応じた手当
・資格手当:会社が指定する資格を保有している場合の手当
・家族手当:扶養家族がいる場合の手当
・出張手当:出張時の補助金
また、欠勤や遅刻による勤怠控除がある場合、ここにマイナス項目として記載されます。
◇控除額
控除額には、給与から差し引かれる税金や社会保険料などが含まれます。おもな控除項目は以下のとおりです。
・所得税:給与額に応じて計算される税金
・住民税:前年の所得に応じて課される税金
・健康保険料:公的医療制度に基づく医療費給付のための保険料
・厚生年金保険料:老後の年金給付のための保険料
・雇用保険料:失業時の給付や育児・介護休業時の給付のための保険料
このほかに、親睦会費や財形貯蓄、寮費といった社内積立金(会社独自の控除)が発生する場合があります。これらの金額は個人の給与や居住地によって異なるため、自分の明細を確認することが大切です。詳しくは次の章で解説します。
◇差引支給額
差引支給額は、いわゆる手取り額のことです。支給額から控除額を差し引いた、実際に支給される給与を指します。支払い方法は、銀行振込か現金支給のどちらかです。
年度途中で昇給があったり、扶養状況が変わったりと変更があった場合は、差引支給額が変動することがあります。従業員側は、振り込まれた金額と給与明細が一致しているかしっかり確認することが大切です。
◇勤務日数などの勤怠情報
給与計算の基礎となる勤怠情報も、給与明細に必ず記載されます。おもな項目は以下のとおりです。
・出勤日数・勤務時間:労働日数および労働時間の合計
・有給休暇取得日数:消化した有給日数
・残業時間・深夜労働時間:残業や深夜労働を行なった時間(割増賃金の計算に必要)
・欠勤・遅刻・早退:給与控除の対象になる場合がある
勤怠情報の記録ミスがあると、支給額や控除額にも影響するため、正しく反映されているか確認することが重要です。
控除額とは?何が引かれているのか

給与明細を見る際に、従業員側が気になるのはやはり、基本給から引かれてしまう控除額でしょう。各種税金や社会保険料などの給与からの控除は、法律に基づいて計算され、企業が従業員に代わって納付する仕組みになっています。具体的にどのような項目が控除されるのか、詳しく見ていきましょう。
◇所得税
所得税は、給与に対して課される国税で、毎月の給与から源泉徴収されます。企業が従業員の代わりに納付し、年末調整で年間の所得をもとに最終的な税額を確定させます。
毎月の所得税額は概算で計算されるため、年末調整で過不足が精算される仕組みです。所得税率は累進課税方式を採用しており、所得が高くなるほど税額も増加します。
◇住民税
住民税は、地方自治体に納める税金で、前年の所得に基づいて課税されます。また、住民税は、所得に応じて決まる所得割と、所得に関係なく一律で課される均等割で構成されています。
会社員の場合、多くは特別徴収として給与から天引きされ、企業が代わりに納付する仕組みです。なお、住民税は前年の所得に基づいて決まるため、新社会人など初めての給与所得者は翌年から支払いが発生します。
◇健康保険料
健康保険料は、従業員が医療サービスを利用する際に必要な社会保険料の一つで、業務外の病気やケガに備えるための制度です。会社員の場合、健康保険組合または協会けんぽに加入し、保険料を会社と折半して負担します。従業員が負担する分の保険料が、毎月の給与から天引きされる形です。
◇厚生年金
厚生年金は、老後の年金や障害年金、遺族年金の給付を目的とした年金制度です。国民年金と連動しており、厚生年金保険料のなかに、国民が必ず納めなければならない国民年金保険料も含まれています。保険料は給与額に応じて決まり、会社と従業員が折半して負担します。
厚生年金は、退職後の生活に備える重要な制度の一つです。厚生年金に加入している期間が長いほど、将来受け取る年金額が増えます。
◇雇用保険
雇用保険は、失業時の生活を支援するための制度で、失業手当や育児、介護休業給付などとして具体化されます。保険料は、事業の種類によって異なり、会社と従業員がそれぞれ負担します。
雇用保険制度への加入は企業側の義務です。また、雇用保険の被保険者となる基本的な条件は、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある場合です。そのほか、雇用形態や役員など立場によって被保険者になる範囲が定められています。
参照厚生労働省「雇用保険の被保険者について」
企業は雇用保険料を毎月控除し、企業負担分と合算して毎年納付します。
◇介護保険(40歳以上)
40歳以上65歳未満の従業員は、介護保険料も給与から控除されます。これは、高齢者の介護サービスを提供するための財源となるもので、健康保険料と一緒に徴収されます。保険料率は保険者ごとに異なりますが、健康保険料と同じく会社と折半で負担する仕組みです。
給与明細の取扱いについて問い合わせを受けたら

給与明細は従業員にとって重要な書類であり、発行や管理には慎重な対応が求められます。万が一、間違いがあった場合には適切な修正対応が求められます。従業員からの問い合わせに備え、給与明細の取扱いについて正しく理解し、迅速に対応できるようにしておきましょう。
◇金額に間違いがないか確認する
給与明細には、支給額・控除額・差引支給額が記載されています。これらの金額が正しく計算されているか確認しましょう。特に、通勤手当は一定額まで非課税となるため、その計算が適切に反映されているかも重要なチェックポイントです。先述したとおり、実際に振り込まれた金額と相違がないかの確認も大切です。
◇勤怠情報に間違いがないか確認する
給与は勤怠データをもとに計算されるため、出勤日数や勤務時間、残業時間が正確に反映されているかの確認も大切です。有給休暇の取得状況や欠勤控除なども確認し、さらには適切でない控除がないかも注意深く確認しましょう。
タイムカードや勤怠管理システムと給与明細を照らし合わせ、不一致があれば早急に報告してもらう体制作りも重要です。
企業によっては、紙の勤務表や手作業での集計を採用している場合もあるでしょう。この場合、集計時の誤りやデータの反映漏れが発生する可能性が高いため、より慎重にチェックをしなければなりません。
◇最低でも5年は保管する
法的には従業員側も企業側も、給与明細の保管義務はありません。しかし、特に従業員に対しては、給与明細は最低5年間の保管が推奨されます。これは、給与未払いの請求期限が5年(当分は3年)であることや、雇用保険の未加入が判明した場合に過去に遡って加入手続きが可能となることによります。
また、給与明細は、住宅ローンの審査や転職時の年収証明としても利用されることがあり、従業員から再発行を求められることもあるでしょう。そうしたシーンを想定し、企業側は給与明細の控えを保管しておくのが賢明です。
給与明細の管理には、紙の書類だけでなく電子データでの保存も有効です。定期的にバックアップを取ることで、紛失や破損のリスクを防ぎ、必要なときにすぐに取り出せるようにしておきましょう。
雇用形態によって給与明細に違いはある?
給与明細は、雇用形態にかかわらず、すべての従業員に対して発行する必要があります。正社員に比べてアルバイトや日雇い労働者の給与明細はシンプルになることが一般的ですが、記載される基本項目は同じです。ただし、手当の有無や社会保険適用の有無により、内容が異なる場合があります。
◇アルバイトの給与明細
アルバイトの給与明細は、基本的に時給制で計算され、働いた時間×時給で支給額が決まります。残業手当や通勤手当が追加されることもありますが、正社員と比較して手当の項目は少なめです。
また、アルバイトでも社会保険加入条件を満たす場合、控除額が変動し、健康保険料や厚生年金保険料が引かれることがあります。加えて、所得税や住民税が課税されると、その分が明細に記載されるため、雇用時間や金額に応じて税務関連も確認が必要です。
◇日雇い労働の給与明細
日雇い労働者も給与明細を受け取る権利があり、たとえ日払いでも必ず明細を渡すことが企業側に義務付けられています。なお、日雇いは1日単位の雇用、日払いは1日単位の給与支払いのことです。
給与の計算は、時給または日給制で、勤務日数によって支給額が変動します。記載される項目は、基本給のほかに危険手当や作業手当が加わる場合もありますが、アルバイトよりもさらにシンプルで記載項目が少ないことが特徴です。
給与明細の発行方法について

給与明細の基本的な発行の流れは、次のとおりです。
1.勤怠データと控除書類を準備する
2.勤務時間を集計する(残業・遅刻・欠勤等確認)
3.支給額を計算し、控除額を差し引く
4.賃金台帳に詳細を記録する
5.給与明細書を作成する
6.給与支給日までに従業員へ交付する
給与明細の発行方法には、紙の給与明細と電子給与明細の2種類があります。
紙の給与明細を渡す方法は、手渡しや郵送です。例えば業務室内に設置し、各人に持って行ってもらうなどもできますが、取り違えや紛失のリスクがあるため、手渡しや電子データでの配布が望ましいでしょう。
一方、電子給与明細は、メールや専用システムを通じて配信され、クラウド上の専用システムでいつでも閲覧できるほか、過去の明細も確認できます。ただし、電子化するには対象従業員の同意が必要です。そのため、同意書の対応が可能な勤怠管理システムを活用するのが便利です。
給与管理は「KING OF TIME」へおまかせ!
「KING OF TIME」は、勤怠管理と給与計算を連携させられるクラウド型システムです。タイムカードやシフト管理と給与計算が自動で連携し、集計ミスをなくします。残業時間の自動集計や法定労働時間のチェック機能も備えており、正確な給与計算をサポートします。
KING OF TIMEの勤怠管理システムは、従業員自身で漏れがないか勤怠をチェックし、管理者側で最終チェックを行なったあと、給与へ自動反映される仕組みです。企業と従業員の双方が事前に誤りがないか確認でき、スムーズな給与処理が可能になります。電子給与明細にも対応し、必要な同意書の承諾もシステム上で完結できます。さらに、短時間勤務者やアルバイト従業員が社保加入条件に合致するかどうかの判定も可能です。
雇用形態の違いや残業の有無、リモートワークなど、多様な勤務状況を一元管理でき、給与明細の発行・管理の負担を軽減して、業務の効率化を強力にサポートします。
■ 無料トライアルのお申し込みはこちら >>>
■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>
まとめ
給与明細には、基本給や各種手当、税金や社会保険料の控除額などが記載されており、実際に受け取る手取り額を確認できます。また、勤怠情報と連動しているため、勤務状況の把握にも役立ちます。企業は適切な給与明細の発行が法的に求められ、従業員側では誤りがないか確認することが大切です。
電子化の進展により、給与明細の管理も容易になっています。給与明細の仕組みを理解し、正しく活用しましょう。
勤怠管理システム「KING OF TIME」は、勤務管理と給与計算を連携し、給与明細の発行や管理までスムーズに処理できます。初期費用0円で導入でき、専門スタッフのサポートも充実しているのが魅力です。
勤怠データと連携して給与業務の手間を削減し、正確な給与管理を実現します。効率的な給与管理をお考えの方は、ぜひ無料トライアルをご活用ください。








