
働き方改革関連法が施行されて以降、時間外労働の是正について、企業として本当に十分な対策ができているのか、不安を感じている方もいるでしょう。
残業の規制がどのように変わったのか、現状の課題は何か、そして企業はどのように取り組むべきかなど、あらためて今の対策が十分かどうか確認することが大切です。法令に違反すれば罰則が科される可能性もあるため、企業にとっては適切な理解と管理が欠かせません。
本記事では、特に残業について、その定義や発生原因、適切な管理方法、さらには勤怠管理システムを活用した実践的な対策までを解説します。
❖ 勤怠管理で知っておきたい残業における基礎知識
❖ 勤怠管理において適切な残業管理が必要な理由
❖ そもそもなぜ残業は発生する?残業管理における4つの課題
❖ 勤怠管理で残業管理を怠ると陥りやすいリスク
❖ 残業を減らすための勤怠管理によるアプローチ
❖ 残業管理に勤怠管理システムを導入する3つのメリット
❖ 「KING OF TIME」の勤怠管理システムなら残業管理もスムーズ
❖ まとめ
勤怠管理で知っておきたい残業における基礎知識
まずは、残業に関する近年の法改正の内容や、残業代の計算方法を確認しましょう。
◇ 残業の概要
残業とは所定の労働時間を超えて働くことで、残業には2種類あります。
1つ目は「法定外残業」です。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間以下と定められています。この基準を超えて業務することを「法定外残業」といい、企業が従業員に法定外残業をさせるためには、36協定の締結が必要です。
2つ目は、「法定内残業」です。
自社の所定労働時間を超えていても、法定労働時間内に収まっている残業は「法定内残業」といいます。
例えば、自社の所定労働時間が6時間で、従業員が1時間残業した場合、合計労働時間は7時間となります。この場合は法定労働時間(8時間)を超えていないため「法定内残業」とされます。
◇ 残業の上限規制の導入
2019年の労働基準法改正によって、残業時間の上限が、⽉45時間・年360時間と定められました。それまでは行政指導の範囲にとどまっていましたが、明確に法律として整備された形です。
中小企業については1年間の猶予期間が設けられ、2020年から適用が始まりました。さらに、2019年の改正時点で適用が猶予されていた自動車運転業務、建設事業、医師についても、2024年からは同様に上限規制の適用が開始されました。
また、この改正では残業規制だけでなく「年次有給休暇の取得」に関する変更もありました。使用者は、労働者に対して年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。
参考: 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
◇ 残業代の計算方法
従業員が法定外残業をした場合、企業側は割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金とは、法定労働時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、または深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合に、通常の賃金に一定の割合を上乗せして支払う賃金のことです。「時間外労働手当」のほかには「休日労働手当」と「深夜労働手当」があり、それぞれ決まった割増率での支払いが義務付けられています。
残業した場合の割増賃金の計算方法は次のとおりです。
60時間以内の残業/1か月:1時間当たりの賃金×法定外労働時間×1.25(割増率25%)
60時間超えの残業/1か月:1時間当たりの賃金×60時間超の法定外労働時間×1.5(割増率50%)
このほか、休日労働は割増率35%、深夜労働は割増率25%となり、残業が重なった場合は別途追加されます(休日労働は法定労働時間が存在しないため追加の発生なし)。
参考: しっかりマスター労働基準法 ー割増賃金編ー|東京労働局
勤怠管理において適切な残業管理が必要な理由

残業管理が求められるのは、単に法律を守るためだけではありません。適切な残業管理が必要な理由を見ていきましょう。
◇ 労働基準法を遵守し、社会的信用を保つため
企業が従業員に法定外残業をさせるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出、割増賃金の支払いなど、法律で定められた要件を満たさなければなりません。
要件を満たさない場合、懲役や罰金の対象になるほか、企業名の公表や是正勧告が行われる可能性もあります。未払い分の残業代を請求される事態も想定され、結果として企業の信用は大きく損なわれるでしょう。
残業管理をしっかりと行い、従業員に必要な対価を支払うことは、企業のクリーンな風土づくりの基盤ともいえるのです。労働基準法を遵守した残業管理は、企業が社会的責任を果たし、社会からの信用を保つために欠かせない取り組みといえます。
◇ 従業員の健康を守り、離職を防ぐため
残業管理は、従業員の心身を守るためにも必要不可欠です。長時間労働は心身の大きな負担となり、過労による健康被害のリスクを高めます。
厚生労働省によると、月80時間を超える残業は脳・心臓疾患などと関連性があるとされています。
残業を適切に管理すれば従業員は健康を維持しやすくなり、モチベーションの向上にもつながります。その結果、企業への帰属意識が高まることで離職が減り、安心して働ける職場環境を提供できるでしょう。
参考: STOP!過労死|厚生労働省
◇ 労働実態を知り、生産性を向上させるため
長時間労働が続けば判断力や創造性が低下し、結果的にミスの増加につながる可能性があります。そのため、残業管理を通じて労働実態を正しく把握することは、生産性向上にも直結します。
そのために、まず残業実態を可視化することが大切です。可視化によって見えてきた、削減可能な業務などの課題を一つずつ解決していきましょう。結果的に、効率的に成果を出す体制をつくることが可能になります。
加えて、残業には割増賃金が発生するため、残業時間を減らすことでコスト削減や経営効率の改善にもつながります。
日本は労働時間が長い一方で生産性が低いとされており、残業の削減は、国際的な競争力を高めるうえでも重要な施策となります。
そもそもなぜ残業は発生する?残業管理における4つの課題

残業を減らすためにはその原因を突き止め、改善する必要があります。ここでは、多く見られる4つの残業発生の要因と課題を解説します。
◇ 1.業務量や業務の進め方に問題がある
従業員の人数に対して業務量が多すぎる場合、いくら効率化を進めても対応しきれず、結果として残業が増加します。また、非効率的な業務手順や見直されずに続いている無駄な慣習も、残業を増やす要因です。
さらに、業務が属人化していると一部の従業員に負担が集中し、特定の人だけが残業せざるを得ない状況にもつながります。
◇ 2.残業が常態化し是正する動きがない
多くの従業員が残業しているために、定時に退勤しにくい雰囲気が生まれているという企業もあるでしょう。このような同調圧力が残業を増加させることも少なくありません。
また、長時間労働が続くと残業への感覚が麻痺してしまい、それが当たり前になってしまいます。
そもそも、管理側や従業員に「残業を減らそう」という意識がなければ残業はどんどん日常化し、意識を変えようにも変えにくくなってしまうのです。
◇ 3.クライアントなど外的要因が影響している
残業は、必ずしも社内の事情だけで発生するわけではありません。例えば、クライアントからの仕様変更や確認待ちによって業務が長引き、残業につながるケースもあります。顧客の状況に柔軟に対応することを重視する職場の場合だと、業務時間が不規則になる傾向があります。
また、イレギュラーな状況に対応する体制が整っていない場合も危険です。従業員の急な欠勤やトラブル発生をカバーしきれず、残業につながる原因となります。
◇ 4.残業管理が適切にできていない
残業を管理する仕組みが不十分であることも、大きな課題の一つです。勤務時間の集計や確認をリアルタイムで行わないと、いつの間にか残業時間が上限を超えてしまっているリスクがあります。
従業員の数が多ければ多いほど、残業時間の把握や確認、調整は難しくなり、管理が追いつかなくなる傾向があります。さらに、在宅勤務やフレックスタイム制を採用している場合には、正確な残業時間を把握することが一層難しくなっているのが実情です。
勤怠管理で残業管理を怠ると陥りやすいリスク
残業管理が適切に実施されない場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。ここでは代表的なリスクを解説します。
◇ 労基法違反になり罰則を受ける可能性がある
残業管理が適切にされておらず、残業時間が上限を超えると労働基準法違反となり、罰則や是正勧告の対象となります。具体的には、労働基準法第119条に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあるため注意が必要です。
法令違反は企業の社会的信用を大きく損ない、長期的な企業活動にも深刻な影響をおよぼす可能性があります。
参考: 労働基準法第119条|e-Gov 法令検索
◇ 従業員のモチベーションが下がり離職者が増える
残業しないと終わらない仕事やサービス残業が当たり前になると、従業員は正当な評価をされていないと感じ、モチベーションが低下してしまいます。そうした状況が常態化すると、特にワークライフバランスを重視する層の定着率は下がり、離職や人材流出につながるでしょう。
また、SNSなどの普及によりネガティブな企業イメージが広がると、優秀な人材が集まらず、採用が不利になるリスクもあります。
◇ 健康被害や労災、賃金未払いなどが訴訟につながる懸念がある
残業時間の管理不足は過重労働につながり、従業員の健康被害や労災認定の原因になりえます。また、勤怠記録が不明確であれば未払い残業代が発生し、従業員から請求を受けたり、訴訟に発展したりするケースもあるでしょう。
未払い残業代に加えて、付加金や遅延損害金の支払いを命じられる可能性もあり、こうした事態は金銭的損失にとどまらず、企業の信用低下に直結します。
残業を減らすための勤怠管理によるアプローチ
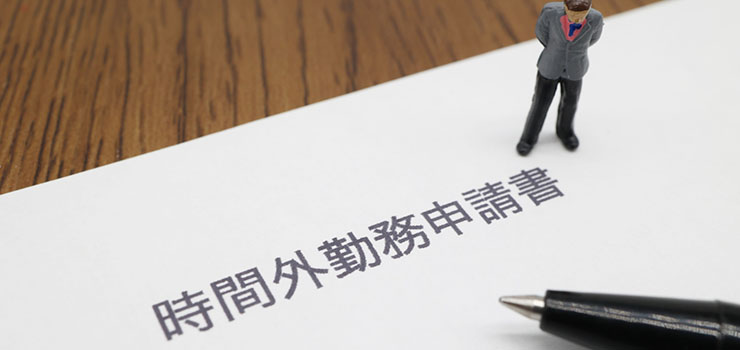
企業が残業削減に取り組む際には、単に「残業を減らそう」と呼びかけるだけでは効果が限定的です。ここでは、残業を減らすための具体的なアプローチを紹介します。
◇ 従業員へのヒアリングやルール周知の実施
残業が発生する原因を明確にするためには、現場の声を聞くことが大切です。従業員へのヒアリングによって、業務の分担や手順に無駄がないか見直し、改善につなげられるでしょう。
また、残業に関するルールを全従業員に周知することも大切です。どのような対策で、どの程度の残業時間を減らすのか明確に示し、全社を挙げて残業削減に取り組むという意識を共有することがポイントです。
◇ 残業申請制の導入
残業申請制とは、従業員が残業を行う際に、事前に上司に申請し、承認を得てから残業する仕組みです。この制度を導入することで、残業の必要性や妥当性を上司がチェックでき、不要な残業を未然に防止できます。業務効率の改善にもつながります。
「残業は当然」という意識をなくし、許可がなければできないものと位置づけることがポイントです。
◇ ノー残業デーの実施
ノー残業デーとは、企業があらかじめ定めた日に原則として残業を禁止し、定時退社を促す取り組みです。長時間労働を抑制し、従業員の健康維持やワークライフバランスの改善、モチベーションアップにつなげられます。
また、定時で帰る習慣が浸透すれば、時間内に効率的に業務を終わらせる意識を定着させられます。
◇ 評価制度の見直し
残業時間の多さを評価基準とする制度は、見直す必要があります。決められた時間内で成果を上げる働き方を奨励し、その姿勢を評価につなげることが大切です。
さらに、報酬制度にインセンティブを組み込み、残業削減に積極的に取り組んだ従業員を正当に評価する仕組みを構築するのも一案です。
◇ 勤怠管理システムの導入
勤怠管理システムを導入すれば、従業員の出退勤や労働時間を自動で記録・集計できます。残業や休日出勤の申請もシステム上で管理できるため、労働時間の把握が容易になり、適切な残業管理が可能です。
システムによってさまざまな打刻方法や機能があるため、自社に合ったシステム選びが大切です。
残業管理に勤怠管理システムを導入する3つのメリット
勤怠管理システムの導入には多くのメリットがあり、上手に活用することで、残業管理の負担を軽減できるでしょう。なかでも、残業管理の効率化につながるメリットを3つ紹介します。
◇ 1.リアルタイムで残業時間が確認できる
勤怠管理システムの大きな特徴は、労働時間を即時に集計し、可視化できる点です。残業時間の積算もリアルタイムで確認でき、個人だけでなく、部署や全社単位での残業状況を素早く把握できます。
こうして可視化されたデータは、残業の原因特定や業務改善に役立ちます。業務量が偏っている人や部署、期間などが見え、業務内容見直しや平準化など、残業削減策を具体的に検討できるでしょう。
また、多様な就業形態を設定できるため、フレックスタイム制やリモートワークなど残業状況が把握しづらい働き方にも対応可能です。
◇ 2.残業時間の上限到達をアラートで知ることができる
勤怠管理システムのなかには、残業時間が法的な上限に近づいた際に通知を行うアラート機能を備えているものもあります。これにより、従業員と管理者の双方がリアルタイムで労働時間を把握でき、労働基準法違反となる前に調整可能です。
業務量や人員配置の見直しなど、対策や改善もスムーズに実施できるようになるでしょう。
◇ 3.勤怠管理の正確性が増し法令遵守につながる
勤怠管理システムによる出退勤記録は、自己申告やエクセル管理などと比べて正確性と客観性に優れています。残業時間も自動計算されるため、人為的なミスを防ぐことが可能です。
割増賃金の対象となる法定外労働時間も正確に算出されるため、未払い残業代のリスク軽減につながります。給与システムと連携させれば、残業時間は割増賃金の算出に自動的に反映され、支払いミスの防止に効果的です。
また、法改正に合わせて自動でアップデートされるシステムであれば、常に法律に準拠した運用を維持できる点も大きなメリットです。
「KING OF TIME」の勤怠管理システムなら残業管理もスムーズ
「KING OF TIME」は、初期費用が不要で、1人当たり月額300円から利用できるクラウド型の勤怠管理システムです。
雇用形態や就業ルールに応じて、休日残業や割増残業などを柔軟に設定できます。従業員はパソコンやスマートフォンから残業申請でき、管理者は承認・却下やコメントの返信を簡単に実施できます。残業時間をリアルタイムで反映し、一定基準を超えた際にはアラート通知や確認メールの送信も可能です。
チャット、電話予約、動画などさまざまなサポート体制が整っているうえ、30日間の無料体験で実際の操作感を試しながら導入を検討できます。
■ 無料体験のお申し込みはこちら >>>
■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>
まとめ
残業が発生する背景には、業務量の偏りや残業の常態化、管理体制の不備など複数の要因が存在します。適切な残業管理は従業員の健康を守り、生活の質を高めると同時に、企業全体の業務効率を向上させる重要な業務です。
勤怠管理システムを導入すれば、残業時間をリアルタイムで把握できるほか、上限到達前のアラート通知や休日管理の効率化も可能になります。結果として、法令遵守の徹底と働き方改革の推進につながるでしょう。
低コストで開始・運用できる「KING OF TIME」は、法改正にも自動対応しており、適切な残業管理に役立ちます。まずは無料体験を通して、ぜひ便利な機能を活用してみてください。








