監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等
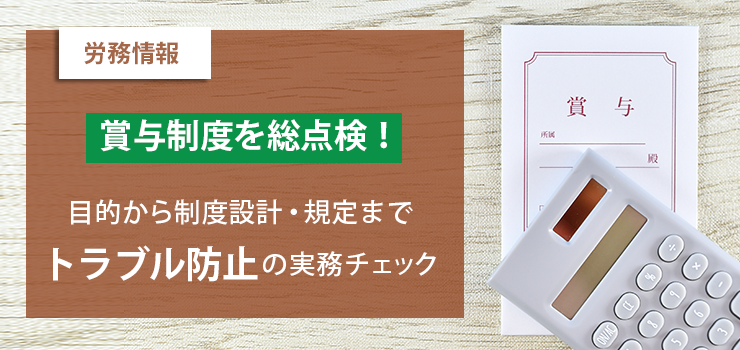
今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ せっかくの賞与支給がトラブルの原因に?
◆ 賞与支給は義務?法的な位置づけ
◆ 賞与の設計パターンと特徴
◆ 就業規則・給与規程で押さえるべきポイント①
◆ 就業規則・給与規程で押さえるべきポイント②
◆ パート・アルバイト社員(短時間・有期契約社員)への対応は?
◆ 会社の方針や想いを伝える仕組みにする
【 KING OF TIME 情報 】
◆ KING OF TIME 給与
せっかくの賞与支給がトラブルの原因に?
賞与(ボーナス)は、単なる報酬の1つではなく、従業員の採用や定着、モチベーションアップなど、会社の施策においても重要な要素です。
また「従業員の喜ぶ顔が見たい」「何とか支給してあげたい」という思いで苦労のうえ支給されている会社も少なくないでしょう。
一方で、賞与に対する認識の相違から、思わぬトラブルにつながるケースもあります。特に、就業規則や雇用契約書、求人票の内容が一致していなかったり運用とズレがある場合は注意が必要です。
すでに賞与を支給している会社も、これから制度化を検討している会社も、賞与について、改めて法的な位置づけと実務上のポイントを整理しておきましょう。
賞与支給は義務?法的な位置づけ
賞与は労働基準法上の「賃金」に含まれますが、支給義務は原則ありません。そのため、会社は任意で制度の有無や設ける場合は内容(支給の条件、金額の算出方法など)を決めることができます。
制度を設けた場合は就業規則に明記が必要です。そして就業規則に規定した内容にそって支給することが「会社の義務」となります。また、長年の慣行で支給を続けてきた場合も、判例上は支払義務が認められることがあるため注意が必要です。(例:支給の継続により黙示の労働契約上の権利が認められるケースなど)
賞与の設計パターンと特徴
賞与制度は、基本的に次の2つのタイプに分けられます。会社の方針(目的や原資の位置づけ、配分方法など)に合わせ①または②、あるいは①と②の組み合わせなど検討できます。
① 固定型
支給額をあらかじめ定めるタイプです。
例:一律10万円、基本給×1か月分など。
・賞与を固定費化。会社業績に関わらず支払義務が生じる可能性があります。
・従業員にとっては、安心感あるが一方、会社業績や個人成績等が反映されません。
② 変動型(業績・成績連動)
会社の業績や個人の成績等によって金額を調整するタイプです。
例:全従業員一律同額で、業績に応じて支給額を変動させる。基準額(基本給など)×係数(〇か月分など、業績や成績を加味)など。
・賞与の変動費化。会社業績に柔軟に対応できます。
・従業員にとって、不安定だが会社業績や個人成績等が反映されます。
その分、従業員の納得感を得るために評価項目や基準の明確化と丁寧なフィードバックの実施が重要です。
なお、支給時期は、一般的には夏、冬、会社ごとの決算期です。決算賞与は会社業績に応じて支給する「特別な賞与」(夏・冬+α)と位置づける会社が多く見られます。
就業規則・給与規程で押さえるべきポイント①
賞与支給の方針を踏まえ、自社の就業規則が方針と一致しているか確認しましょう。
例えば、方針と規定が一致していない場合、トラブルの原因となったり、意図しない対応を迫られる可能性もあるため注意しましょう。
方針:前述の②のように、会社方針が業績に応じて支給の有無を決定したり、本人の勤務成績により支給額を増減させる。
規定:前述の①のように、賞与は毎年7月10日と12月10日にそれぞれ基本給の1か月分を支給する
➡会社の方針や実際の業績に関わらず、規定どおりに支払う義務が生じます。
【②の場合の規定例】
賞与は会社業績に応じ、社員の勤務成績、能力評価など総合的に勘案し、支給の有無、金額を個別に決定します。
会社の状況は社会情勢、景気動向に左右されることもあるため、賞与を支給するつもりでも、やむを得ず不支給としたり、減額して支給したりすることもあるでしょう。業績がよいときを前提に方針を定めると、環境変化への対応が難しくなることもありえます。
また、規定を具体的に決めすぎると柔軟な対応が難しくなります。逆に曖昧すぎると社員の不安や不満にもつながるため、そうした点も含め、会社方針や運用も踏まえた検討が大切です。賞与支給の有無や支給する場合の金額、支給時期等、規定で会社に明確な裁量を持たせることで、負担軽減やリスク回避をすることができます。
規定の見直し時は「不利益変更」となる可能性もあるため、社員への丁寧な説明と同意取得を忘れずに行いましょう。
改めて、今の規定内容が本当に自社(経営者)の考えと合っているかどうか、運用も含めて検討されているのかチェックしてみましょう。
就業規則・給与規程で押さえるべきポイント②
支給する場合の支給時期や算定期間、対象者などを明確にすることで、認識のズレやトラブル防止、実務上もスムーズな対応ができます。
特に入社や退職者、休職者などについては、誤解が生じないよう規定を基に丁寧に説明しておきましょう。
(1)支給時期と算定期間
算定期間と支給日をセットで明記しておきましょう。従業員の評価を行う場合は、評価や賞与額の決定のため、両者の期間を少し空けることも一案です。
例:「算定期間:前年10月~当年3月、支給日:当年6月」
(2)支給対象者
入社・退職・休職のタイミングによって、対象とするか否かを明確に記載しておきます。
例)
・支給日に在籍する社員に支給する
ex.支給日に在籍する者に限り、賞与を支給します。
・入社6か月未満の従業員は対象外(新卒:4月入社の夏の賞与は払わない)
ex.支給日時点で入社後6か月を経過した者を対象とします。
・休職期間中は不支給
ex.算定期間の全期間を休職していた社員は支給対象から除きます。
・勤務成績が悪い従業員は除くケース
ex.「勤務成績が不良でない者」)
・懲戒中の従業員は除くケース
ex.懲戒処分中の者を除く
・在籍や勤務日数に応じて支給額を調整(按分)するケース
ex.賞与の算定期間に対する在籍期間(出勤日数)に応じて按分します。
パート・アルバイト社員(短時間・有期契約社員)への対応は?
同一労働同一賃金の観点から、単にパート・契約社員だからという理由だけで一律に支給対象外とするのは避けるべきです。ガイドラインでは、賞与を会社の業績等への貢献度に応じて支払う場合、貢献度に応じて支給が必要とされているためです。
賞与に関する過去の判例では、結果的にパート・アルバイト社員に対する賞与不支給は不合理ではないとされたケースもありますが、後述のような観点や賞与支給の目的等、諸々の事情を考慮された上で問題ないと判断された結果であることに留意が必要です。
また、パートタイム・有期雇用労働法では、「待遇決定に際しての考慮事項」「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、パート・アルバイト社員の求めに応じ、説明する義務も課されています。
職務の内容や責任、転勤・人事異動などによる職務・配置変更の可能性の観点から正社員との違いを整理し、正社員用・パート用で就業規則を分けて作成するなどし、合理的な待遇差とその説明根拠を明確化しておきましょう。
会社の方針や想いを伝える仕組みにする
賞与は金額の多寡以外にも「何を評価して支給するのか」「どんな想いを込めて支給するのか」を伝えることで、従業員の満足度や会社と従業員との信頼関係を深める重要な機会にもなります。
制度の見直しや運用の整備を通じて、トラブル防止はもとより、「会社の方針を伝える仕組み」の1つとして賞与制度の有効活用を検討してみてはいかがでしょうか。
KING OF TIME 情報
賞与計算や支給時の運用には、KING OF TIME 給与の活用が有効です。
KING OF TIME勤怠管理と自動連携し、勤怠データをもとに、在籍状況を正確に反映した賞与計算を行えます。勤怠と給与を一元管理することで、手入力や確認作業の手間を減らし、賞与支給時のトラブル防止と業務効率化に貢献します。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








