監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
社会保険労務士 岩下 等
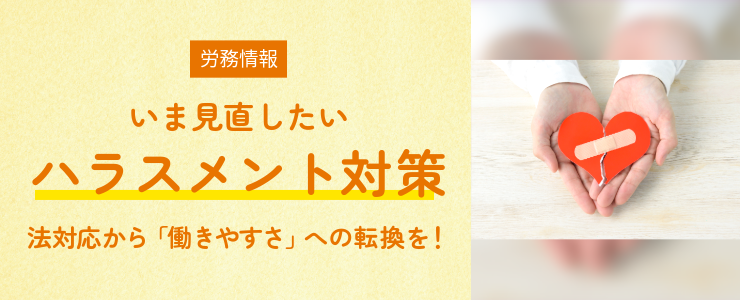
今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ リスクを認識し対策の実効性を高める機会に
◆ 広がるハラスメントの概念と義務化の流れ
◆ 法整備の効果と新たな課題
◆ 制度整備だけでは防げない現場の実態とは?
◆ 相談件数自体は依然高水準、制度の形骸化も課題
◆ ハラスメントが起きやすい職場の特徴をチェック
◆ 相談しても無駄?対応の形骸化が招く組織不信
◆ 実効性を高める2つのカギ
◆ ハラスメント対策はコストではなく、企業価値向上の投資
【 KING OF TIME 情報 】
◆ KING OF TIME データ分析
リスクを認識し対策の実効性を高める機会に
パワハラ防止法の全面施行から2年。
制度整備を進めた企業も多い一方で、現場では「相談しても変わらない」「制度が形骸化している」といった声も聞かれます。
厚生労働省では、毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
近年、ハラスメント対策の法制化が進み、社会的な認知も大きく広がりました。
しかし、企業によっては規定や体制の整備が十分でなかったり、形式的な対応にとどまり、実際の防止効果が伴っていないケースも少なくありません。
厚生労働省は、ハラスメントの問題について次のように指摘しています。
働く人にとって、
・働く人が能力を十分に発揮することの妨げになる
・個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為である
企業にとって、
・職場秩序の乱れや業務への支障が生じる
・貴重な人材の損失につながる
・社会的評価にも悪影響を与えかねない
ハラスメントが発生すれば、従業員の心身の健康を害するだけでなく、企業の信頼性や経営基盤を揺るがしかねません。いま求められているのは、「制度を整える」段階から、「実効性を高める」段階への移行です。
この撲滅月間を機に、社会の動向や最新のリスクを踏まえ、自社の運用体制や実施状況を見直し、未然防止と企業内外から信頼される組織運営の強化を図っていきましょう。
広がるハラスメントの概念と義務化の流れ
かつてハラスメントは、「職場での個人的なトラブル」として扱われることが多く、企業の取り組みも努力目標程度にとどまっていました。しかし近年、社会の価値観や働き方の多様化などを背景に、組織的に取り組むべき課題として位置づけられ、防止措置の義務化が段階的に進み、その対象範囲も拡大してきました。
こうした流れから、「ハラスメント対策」はコンプライアンスのみならず、経営ガバナンスの重要な施策であるとも言えるでしょう。制度の整備や現場運用に加え、組織文化や意識改革を伴う質の高い対策が今、企業に求められているといっても過言ではないでしょう。
■主な流れ
【法的義務】
・セクシュアルハラスメント
1999年:男女雇用機会均等法改正
➡職場におけるセクハラ防止措置を初めて事業主の義務として明文化。
・マタニティハラスメント
2017年:男女雇用機会均等法改正
➡妊娠・出産に関するハラスメントの防止措置を義務化。
・育児・介護関係ハラスメント
2017年:育児・介護休業法改正
➡育児・介護休業の取得等を理由とするハラスメントの防止措置を義務化。
・パワーハラスメント(大企業/中小企業)
2020年/2022年:労働施策総合推進法改正(いわゆるパワハラ防止法)
➡職場におけるパワハラ防止措置を義務化。
方針の明確化、相談体制の整備、迅速な対応などが法的要件に。
【努力義務】
・カスタマーハラスメント
2022年:厚生労働省指針
➡顧客や取引先などからの暴言・威圧・過度なクレーム等への防止対応を、企業の努力義務として明示。
・就活・採用ハラスメント
2022年以降:厚労省指針・通達レベル
➡採用選考・インターンシップ等におけるセクハラ防止を要請。
現時点では努力義務・行政指導の段階にとどまる。
【検討中・改正予定(法令化の方向性)】
・自爆営業(過度なノルマ強制)
2025年以降(予定):2024年「規制改革実施計画」(2024年6月閣議決定)に基づき、パワハラ防止指針の改正が検討中。
➡業務上必要な範囲を超える過度な販売ノルマや自費購入の強制(いわゆる「自爆営業」)を、パワハラ行為として明確に位置づける方向性が示されている。
【国際的動向】
・ILO(国際労働機関)第190号条約
2019年採択:仕事の世界における暴力・ハラスメント撤廃を目的とする国際条約。
➡日本では批准に向けた国内法整備と包括的な国内対応の検討が進められています。
職場内外を問わず、あらゆる働く場における暴力・ハラスメントの排除をめざす国際的な流れは、ILO190号条約にも象徴されています。
法整備の効果と新たな課題
法整備が進み、実態はどのように変化してきたのでしょうか。
厚生労働省が公表した「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、2020年のパワハラ防止法(大企業対象)施行以降、企業内でのパワハラやセクハラの相談件数の増加傾向には、一旦の歯止めが見られます。企業による意識の向上や体制整備が一定の成果を上げているといえるでしょう。
一方で、顧客や取引先など外部からの迷惑行為、いわゆるカスハラは増加傾向にあり、企業経営を脅かすリスクとしてその認知も高まってきています。
過去3年間にカスハラの該当事例があった企業は約3割。特に顧客対応が多い業種で発生率が高く、内容としては「執拗なクレーム」「暴言」「威圧的な言動」などが目立ちます。
被害を受けた従業員の6割以上が「精神的な不安や怒りを感じた」と回答しており、こうしたストレスが業務への支障や離職につながるケースも少なくありません。
今やカスハラは、職場の安全配慮義務や人材定着戦略とも密接に関わるテーマとなっています。
制度整備だけでは防げない現場の実態とは?
調査のなかで特に参考になる項目として、「ハラスメントが発生した職場の特徴」、「ハラスメント発生後の行動(労働者・企業)」があります。
まず、「ハラスメントが発生した職場の特徴」として共通点が見られます。
それは「常に人手不足」「長時間労働」「コミュニケーション不足」といった慢性的なストレス環境です。
心身ともに高い負荷がかかり、かつそれが常態化している職場では、上司・部下双方の心理的余裕が失われ、結果として不適切な言動が増加しやすくなることが想像されます。
つまり、ハラスメント防止は特定の行為者・被害者のみへ焦点を当て、その問題を解決するだけにとどまらず、職場全体の働きやすさ・負担やストレス軽減策と一体で進めるべき課題といえるでしょう。
次に「ハラスメント発生後の行動」では、ハラスメントを受けた人の約4割が「何もしなかった」と回答し、その理由の多くが「何をしても解決にならないと感じた」としています。
その背景には、企業がハラスメントの事実を認識しながら「特に何もしなかった」との回答が多いことも影響し、ハラスメントを受けた人が「相談しても変わらない」と企業への不信感も垣間見られます。
つまり、単に法令対応として制度を整備しただけでは、実際の抑止効果は限定的であり、本当の意味でのハラスメント防止には、制度の整備と並行して、相談しやすい風土づくりと組織への信頼醸成も欠かせないといえるでしょう。
これらの実態や原因についてさらに掘り下げ、ハラスメント対策の実効性を高めるための視点を整理していきましょう。
相談件数自体は依然高水準、制度の形骸化も課題
過去3年間にハラスメントの相談があった企業の割合は、パワハラは約6割、セクハラは約4割と依然として高い水準です。
ハラスメントの種類別に企業が把握している相談件数の傾向は、「減少」「増加」「変わらない」のうち、最も多いのは「変わらない」でした。ただし「減少」と「増加」の比較では「減少」が「増加」を上回っており、法改正に伴う企業の取組が一定の効果を上げ始めていることが読み取れます。
一方で、育児休業等に関するハラスメントについては、男女ともに2~3割が、過去5年間にハラスメントを受けた経験があると回答。特に男性ではそのうち、2~3割が「育児休業」や「所定外労働免除等」の制度の利用を諦めています。
制度は設けても実際には、職場の文化や状況などさまざまな要因により使えない(使いづらい)ことは大きな課題といえます。
ハラスメントが起きやすい職場の特徴をチェック
パワハラ・セクハラを経験した人が指摘した職場の特徴(経験しなかった人よりも10ポイント以上高い項目)については、次のような傾向があります。
ハラスメントの発生の一因は、職場の余裕のなさとも考えられます。そのため、ハラスメントの原因を安易に個人の気質などの問題に落し込むのではなく、会社の問題として俯瞰してさまざまな面からとらえる必要もあります。
■主な特徴(パワハラ・セクハラ)
・「人手が常に不足している」などがある
・残業が多い/休暇を取りづらい
・上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない
・失敗が許されない/失敗への許容度が低い
・従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる
・従業員の年代に偏りがある
・ハラスメント防止規定が制定されていない
相談しても無駄?対応の形骸化が招く組織不信
ハラスメントを受けた人が、その後「何もしなかった」と回答した割合は、パワハラで3割半ば、セクハラに至っては5割に達しています。
その理由は「何をしても解決にならないと思った」が最も多い結果となっています(パワハラ6割半ば、セクハラ5割)。
この背景には、ハラスメントに対する企業側の姿勢も影響していることが考えられます。ハラスメントを企業が認識したにもかかわらず、パワハラで5割超、セクハラで4割超が「特に何もしなかった」と回答しているのです。
つまり、事案が認識されながら放置されるケースも多く、これが従業員に「相談しても無駄」と認識させ、ハラスメントを受けても何もしないという結果に至り、さらにはハラスメントが潜在化する(企業は問題やリスクに気づかない)要因にもなっていると考えられます。
形式的な相談窓口では不十分であり、公正・中立で実行力が伴う対応が求められます。
実効性を高める2つのカギ
これまでお話してきた内容に加え、ハラスメントの取り組みを進めるうえでの課題として、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」が最も高く、次いで「管理職の意識が低い/理解不足」と「発生状況を把握することが困難」が挙げられています。
これらを踏まえ、ハラスメント対策の実効性を高めるうえでは、以下がポイントとなります。
■管理職・相談担当者への実務研修
・判断基準、ヒアリング方法、対応記録など、実践的知識を体系的に学ぶことで「曖昧処理」を防止。
➡迅速かつ公正な対応を組織に定着させる。
■組織ストレスの根本改善
・業務量の適正化、長時間労働の是正、コミュニケーション設計など、ハラスメント防止を「働き方改革の延長線」として捉える。
➡調査でも多くの労働者が「職場環境の改善」を求めている。
ハラスメント対策はコストではなく、企業価値向上の投資
ハラスメント防止は、罰則回避のためのコストではなく、組織の成長力を高める投資です。
企業調査では、取り組みを進めた企業のうち、
・職場のコミュニケーションが活性化した(約4割)
・会社への信頼感が高まった(約3割半)
という成果が出ています。
労働者調査でも、積極的に取り組む職場では
・生産性
・働きやすさ
・上司・部下の関係
が改善したとの回答が多数を占めています。
ハラスメント対策は、企業の法的義務であると同時に、人材定着・生産性向上・企業価値向上を実現する経営戦略です。
制度を整えるだけでなく、現場で機能する仕組みづくりを進めることが、企業の信頼と成長を支える最大の鍵となります。
KING OF TIME 情報
ハラスメントの背景には、長時間労働や過重な業務負担など、職場のストレス環境が関係することもあります。「KING OF TIME」は、勤怠をリアルタイムで管理できるクラウドシステムです。
残業や休日出勤が一定時間を超えると自動で通知するアラート設定があり、過重労働を早期に把握できます。
さらに、KING OF TIME データ分析を活用すれば、部署や期間ごとの勤務傾向を可視化し、職場環境の改善やリスク防止に役立てられます。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








