監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄
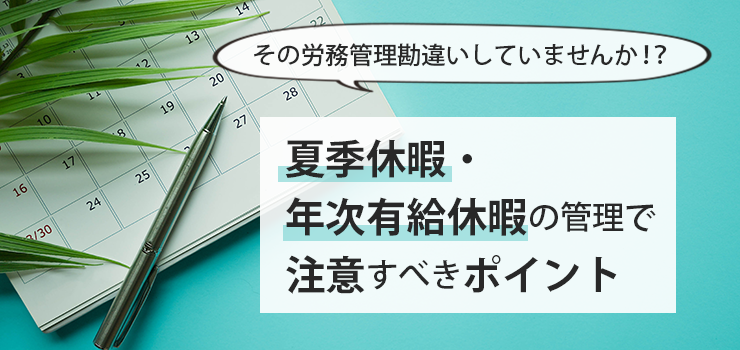
今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ 夏季休暇と年次有給休暇の違い
◆ 夏季休暇に関するよくある勘違い
◆ 夏季休暇と年次有給休暇の運用のポイント
◆ 勤怠管理システムの活用がおすすめ
【 KING OF TIME 情報 】
◆ KING OF TIME 勤怠管理|休暇管理機能
夏季休暇と年次有給休暇の違い
6月、7月頃になると、社員から「夏季休暇はいつから取れるのか?」「有給休暇と合わせて長期連休にしても問題ないか?」などの問い合わせが出てきます。この夏季休暇と年次有給休暇、ふだん何気なく扱っていらっしゃる方も多いと思いますが、実は法的な扱いがまったく異なることをご存じでしょうか?
いずれも「休暇」ではありますが、夏季休暇は年次有給休暇と違って、法律で義務付けられている休暇ではありません。そのため、そもそも企業が夏季休暇制度を導入するか否かは任意であり、制度を設ける場合はその内容(付与日数や付与する時期、有給か無給かなど)も会社ごとに決められます。決めた内容については、年次有給休暇と同じく、就業規則や雇用契約書に付与日数や取得期間を明文化しておく必要があります。
・夏季休暇:就業規則や企業の慣行による任意の休暇
・年次有給休暇:労働基準法第39条で規定された法定休暇
年次有給休暇については、2019年の法改正により「年5日の有給休暇取得」が企業に義務付けられ、その管理は一層重要になっており、正しい知識がないまま運用していると、法令違反や社内トラブルにつながるおそれがあります。
今回は夏季休暇に関する「よくある勘違い」を交えつつ、正しい運用のポイントを解説します。
夏季休暇に関するよくある勘違い
① 夏季休暇は法律で定められた休暇だと思っている
前述のとおり、夏季休暇は労働基準法などで義務付けられた休暇ではなく、企業が独自に設定・運用する「任意の休暇」です。企業が導入していないからといって、違法というわけではありません。一方で、夏季休暇を設けていても、付与日数や対象者などを明確に規定しておかないと、従業員との認識違いなどによりトラブルにつながりやすい点に注意しましょう。
② 夏季休暇と年次有給休暇の区別が曖昧で混同している
年次有給休暇は法定休暇として取得日数や管理簿の作成など厳密なルールがあるため、両者を混同すると、日数や残日数の管理を誤りやすくなります。例えば「夏季休暇を取ったはずなのに有給休暇が減った」というケースは典型例です。就業規則やシステム上で夏季休暇を別枠として管理し、従業員にも明確に周知しましょう。
③ 法定休日や振替休日と夏季休暇を同じ扱いにしている
週1回以上の法定休日は労働基準法第35条で義務付けられており、その休日の労働に対しては割増賃金が適用されます。関連して、振替休日も法定休日を別日に振り替える仕組みであり、いずれも夏季休暇とは性質が異なります。同一視すると、法定休日数が不足したり、割増賃金が正しく支払われないなどのリスクが生じるため、夏季休暇を別枠で管理し、休日数や賃金計算を正確に行うことが重要です。
夏季休暇と年次有給休暇の運用のポイント
① 就業規則で夏季休暇の内容を具体的に定める
夏季休暇を導入する際は、「日数」「期間」「対象」「取得方法」「給与支払いの有無」などを就業規則で明示しましょう。任意休暇だからこそルールがあいまいだとトラブルが起きやすくなります。決まった日を休暇とする方法や、個々の都合に合わせて取得する方法など、どの制度を採用するのかをはっきり決めておくことが大切です。
② 年次有給休暇と組み合わせる際の注意点
企業によっては、夏季休暇と年次有給休暇を組み合わせて長期休暇とするケースが見られます。ただし、年次有給休暇は従業員の請求に基づくものなので、企業が一方的に取得日を指定することは基本的にできません。一方で、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員には、年5日を必ず取得させる義務があります。そのため、夏季休暇と組み合わせて積極的に年次有給休暇の取得を促すことは、この義務を果たすためにも有効です。
③ 計画的付与制度や時間単位有給の活用
年次有給休暇の取得率向上に「計画的付与制度」を利用する企業もあります。これは、年次有給休暇のうち5日を除く分を企業があらかじめ取得日を定める仕組みです。夏季休暇や年末年始などと組み合わせると、長期休暇の促進につながり効果的な休暇取得が期待できます。また、労使協定を締結すれば、年次有給休暇のうち5日分を上限に時間単位で取得できます。ただし、時間単位で取得しても年5日の取得義務に対しては取得日数としてカウントできません。また、時間単位の管理は複雑になるため、勤怠管理システムでの管理が望ましいでしょう。
勤怠管理システムの活用がおすすめ
① 年次有給休暇の消化状況を可視化する
年5日の年次有給休暇取得義務に対応するには、従業員ごとの取得状況を把握し、未取得者には計画的取得を促す必要があります。紙やエクセル管理ではヒューマンエラーが発生しやすく、リアルタイムの残日数管理も難しくなります。勤怠管理システムを導入すると、有給申請や申請・確認のフローが自動化され、夏季休暇との併用状況も一目でわかりやすくなります。
② 夏季休暇とその他の休暇を正しく区分する
夏季休暇、年次有給休暇、法定休日、振替休日などは、それぞれ根拠や取り扱いが異なります。勤怠管理システムで『休暇区分』を設定することで、申請時の間違いが減り、管理者も消化状況を正確に把握できます。
③ 専門家への相談と社内周知が不可欠
システム導入だけでなく、就業規則や労使協定、法改正を踏まえた運用ルールを整えることが大前提です。業種や勤務形態によっては複雑なケースもあるため、社会保険労務士やシステムベンダーなどの専門家に相談するのがおすすめです。新制度の導入や規則改訂時には、社内への周知やQ&A形式のマニュアル整備も欠かさないようにしましょう。
夏季休暇と年次有給休暇は、従業員がリフレッシュして生産性を高めるうえで欠かせない制度です。しかし、両者の違いを誤解したまま運用すると、法令違反やトラブルにつながりかねません。就業規則や勤怠管理システムを適切に活用し、従業員が休みやすい環境を整えると同時に、法定休暇と任意休暇を明確に区別して管理することが重要です。
KING OF TIME 情報
夏季休暇と年次有給休暇は、制度の成り立ちや法的義務が異なるため混同に注意が必要です。
KING OF TIMEの休暇管理機能は、有給休暇、代休、年次有給休暇などに加え、企業独自の休暇管理や、全日、半日、時間単位での有休設定が可能です。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。








